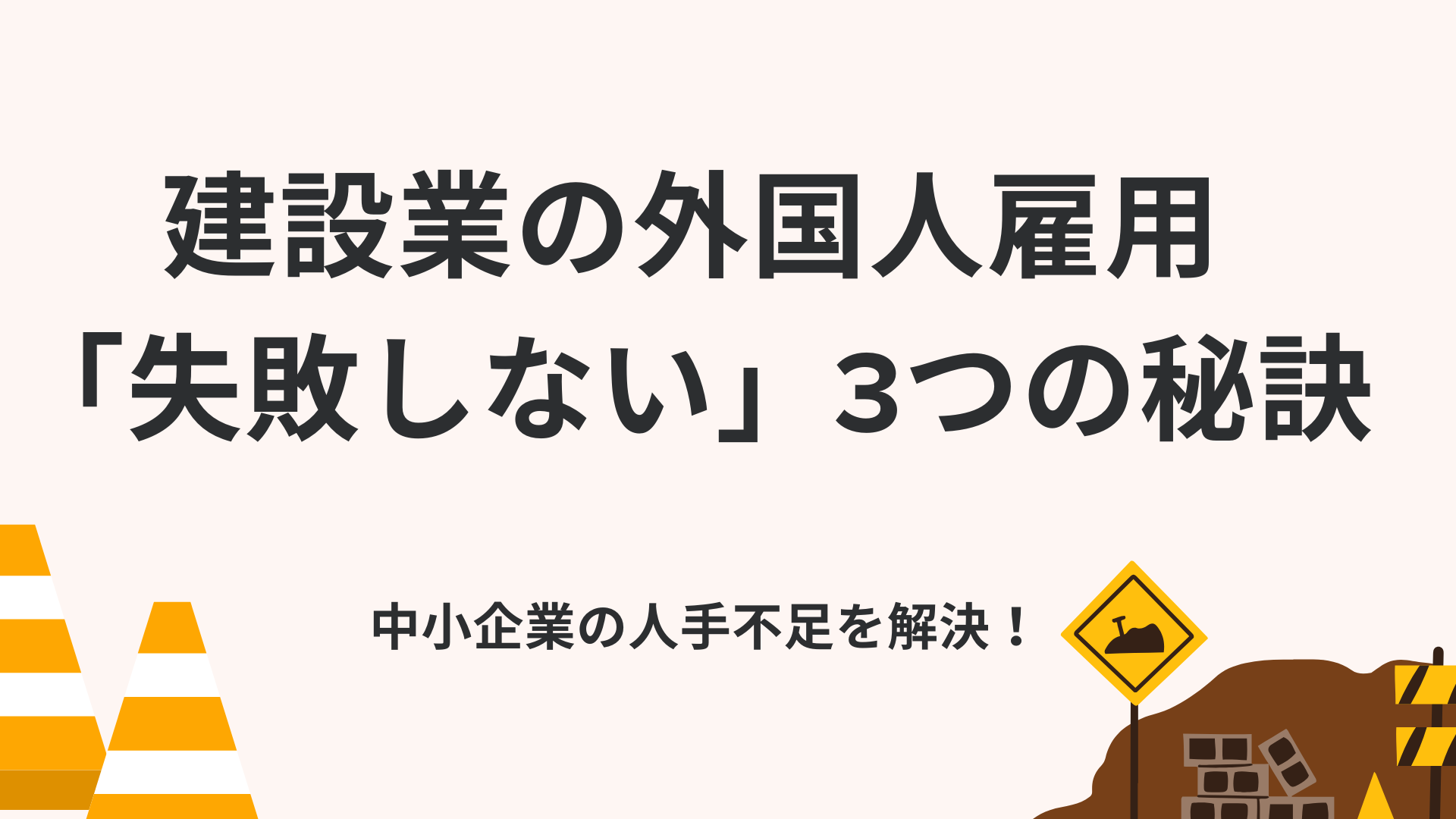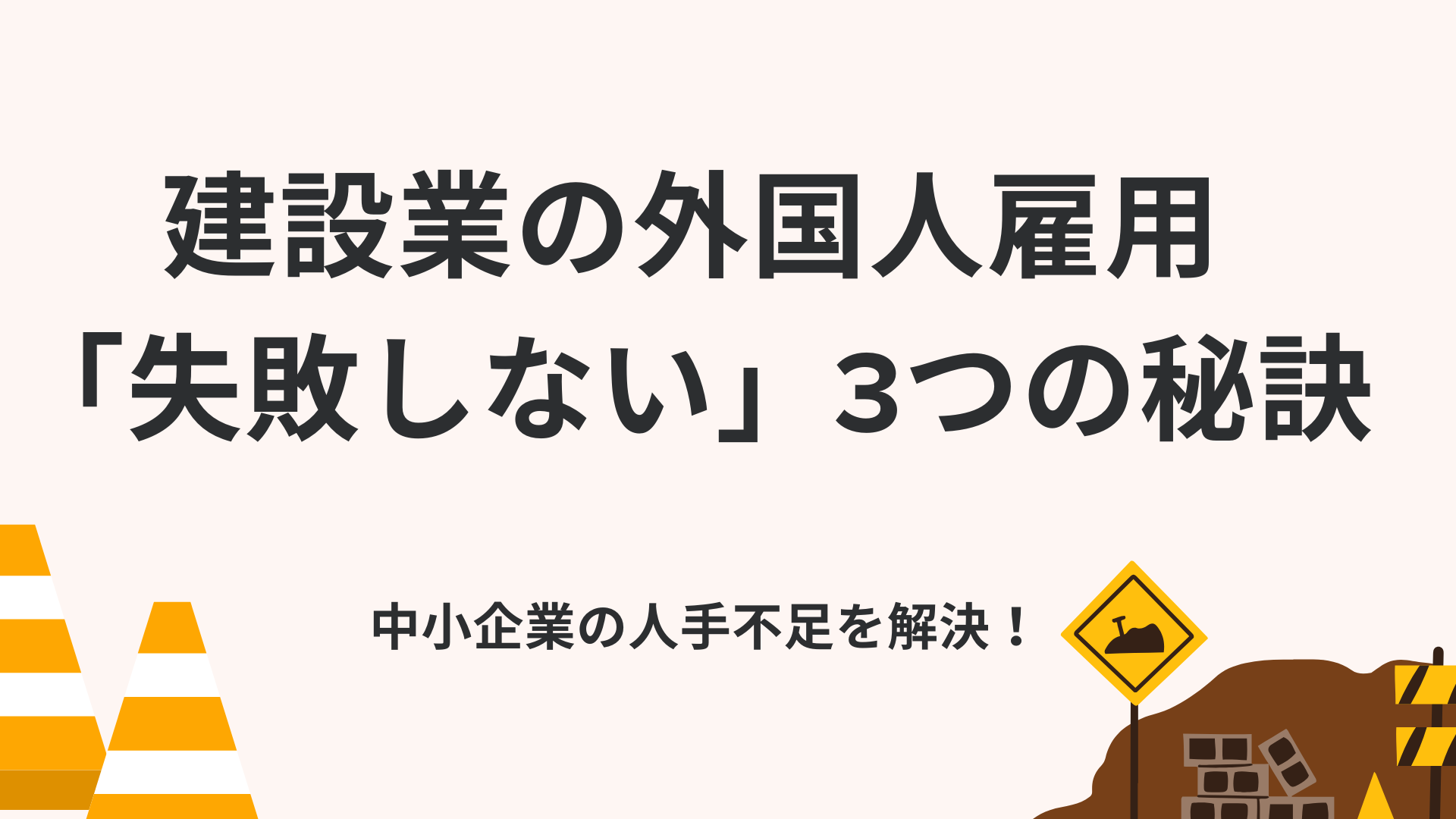
「新しい工事を受注したいけれど、慢性的な人手不足で断らざるを得ない」「長年支えてくれたベテラン職人の高齢化が進み、この先の現場が不安」…建設業を営む企業も、このような悩みを抱えていませんか?「外国人労働者の雇用も考えたけれど、手続きが複雑そうだし、言葉の壁や定着も心配で、結局一歩踏み出せない」という声もよく耳にします。もしかしたら、「どうせウチには無理だろう」と諦めかけているかもしれません。
本記事では、そんな不安を解消し、建設業における外国人労働者活用の「現実的な可能性」と「成功へのロードマップ」を明確に提示します。特定技能制度の基本から、煩雑な手続きを円滑に進める秘訣、そして外国人材が長期的に活躍し、日本人社員と共に成長する現場を作るための定着ノウハウまで、具体的なステップで解説します。
目次
建設業の「人手不足」は深刻化!外国人材活用が不可欠な理由

建設業界では、慢性的な人手不足が深刻化しています。これは、新しい工事の受注機会を失うだけでなく、技術継承の危機にも繋がりかねません。このような状況を打開するため、外国人材の活用が不可欠となっています。
■建設業における外国人労働者の現状と増加トレンド
日本の建設業で働く外国人労働者は年々増加しており、その存在感は無視できません。
厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末現在)によると、日本の建設業で働く外国人労働者は約18万人に達し、前年比22.7%増と急速に増加しています。特に「特定技能」という在留資格を持つ外国人材は即戦力として期待されており、特定技能1号の外国人材は38,365名に上ります。一方で、特定技能2号はまだ213名にとどまっているのが現状です。これは制度が発展途上であると同時に、長期的な人材確保の大きな可能性を秘めていることを示しています。
■なぜ今、外国人材の活用が中小建設業に必須なのか?
建設業の人手不足は、日本人労働者の高齢化と若年層の業界離れという構造的な問題に起因します。ハローワークや求人サイトを使っても、なかなか若い日本人が応募してこない、というお悩みは中小企業で特に顕著でしょう。
外国人材は、この人手不足を補う「即戦力」として、そして会社の「長期的な戦力」として期待されています。外国人材の活用は、単なる「穴埋め」ではありません。むしろ、会社の「未来への投資」であり、まるで雨が降る前に「雨水を貯めるダム」を作るようなものです。将来の仕事量や技術継承に備え、今から手を打つことが、企業の安定した成長には不可欠と言えるでしょう。
建設業で外国人材を雇用する主要な在留資格制度を徹底解説
外国人材を雇用する際には、いくつか在留資格の種類があります。ここでは、特に建設業で注目すべき制度について、分かりやすく解説します。
■特定技能制度とは?建設業が注目すべき理由
特定技能制度は、日本国内で人手不足が深刻な特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。建設業もこの特定産業分野の一つとして指定されています。
建設分野における特定技能の対象職種は多岐にわたります。例えば、
型枠工事、左官工事、屋根工事、電気通信工事などが挙げられます。これらの職種で必要な技能と日本語能力を持つ外国人材が対象となります。
外国人材を受け入れる企業が満たすべき主な要件としては、
建設業法第3条の許可を受けていること、
建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、そして
建設技能人材機構(JAC)への加入などが義務付けられています。これらの要件は、外国人材が安心して働ける環境を確保するために設けられています。
特定技能制度の詳しい要件に関する詳細記事へ
■技能実習制度との違いと育成就労制度の最新動向
外国人材の受け入れ制度として、
特定技能制度の他に
技能実習制度があります。両者には目的や期間、転籍の有無などに大きな違いがあります。

技能実習制度は、国際貢献を目的としているため、在留期間が限定的で転籍も原則認められません。そのため、長期的な人材確保には課題がありました。
こうした背景から、
2024年の通常国会で「育成就労制度」を創設する法案が成立し、2025年中の施行が見込まれています。この制度は、技能実習制度の課題を解決し、人材育成と人材確保を両立させることを目指しています。
育成就労制度で一定の経験を積んだ外国人材が特定技能制度へ円滑に移行できるようになることで、企業はより長期的な視点で人材計画を立てられるようになるでしょう。
■特定技能2号で「長期雇用」が可能に!その条件と職種
特定技能制度には、
特定技能1号と
特定技能2号があります。特定技能1号は最長5年の在留期間ですが、特定技能2号に移行することで、
在留期間の上限がなくなります。これは、外国人材が単なる「アルバイト」ではなく、「正社員」として腰を据えて働けるようになる
パスポートのようなものです。
特定技能2号の大きなメリットは、長期雇用が可能になるだけでなく、
家族を日本に呼び寄せることが可能になる点です。これにより、外国人材が日本での生活基盤をより安定させ、安心して長期的に働くモチベーションに繋がります。
建設分野における特定技能2号の対象職種は、特定技能1号で認められている全ての職種が対象となります。ただし、求められる技能レベルはさらに高く、熟練した技能が求められます。
特定技能2号の要件に関する詳細記事へ
「失敗しない」建設業の外国人雇用:成功への3ステップ

「外国人材の雇用は初めてで、失敗しないか不安だ」というお悩みはよく聞かれます。しかし、正しいステップを踏めば、その不安は大きく解消できます。ここでは、成功に向けた3つのステップをご紹介します。
■ステップ1:受け入れ体制の整備と必須要件の確認
外国人材を受け入れる前に、社内の準備をしっかり行うことが成功の鍵です。受け入れ体制の整備は、家を建てる前の「地盤固め」のようなもの。しっかり準備すればするほど、後々のトラブルを防ぎ、安定した基盤ができます。
具体的には、以下の準備が必要です。
- 社内体制の整備: 外国人材の受け入れ担当者を決め、役割を明確にします。
- 日本人従業員への説明: 外国人材を受け入れる目的や、共に働く上での心構えなどを事前に説明し、理解と協力を促します。
- 多文化理解の促進: 外国人材の文化や習慣を学び、お互いを尊重できる職場環境を目指します。
また、建設業で特定技能外国人材を受け入れるには、いくつかの必須要件があります。
- 建設業法第3条の許可: 建設業を営む上で必要な許可です。
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録: 技能者の就業履歴や保有資格を蓄積するシステムで、建設業の適正な評価に繋がります。登録は必須です。
- 建設技能人材機構(JAC)への加入: 特定技能外国人材の適正な受け入れを支援する機関です。加入が義務付けられています。
これらの要件を満たすことが、適正な外国人材雇用の第一歩となります。
■ステップ2:外国人材の募集から採用までの流れ
受け入れ体制が整ったら、いよいよ外国人材の募集と採用に進みます。
外国人材の募集方法はいくつかありますが、
人材紹介会社や
登録支援機関の活用が一般的です。専門の会社に依頼することで、求める人材を効率的に見つけ、ビザ申請などの煩雑な手続きもスムーズに進められます。
選考時には、単に日本語能力や技能レベルだけでなく、企業文化に合うか、長期的に働く意欲があるかといった
人物像の見極めが重要です。面接では、具体的な業務内容や職場の雰囲気を丁寧に伝え、相互理解を深めることが大切です。
採用が決まったら、
在留資格(ビザ)の申請手続きを行います。この手続きは複雑で専門知識が必要なため、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。
■ステップ3:入社後の定着支援とトラブル予防策
外国人材が採用されたら終わりではありません。入社後の
定着支援は、早期離職を防ぎ、生産性を向上させるために非常に重要です。
具体的な定着支援策としては、以下のようなものが挙げられます。
- 生活支援: 住居の確保、銀行口座開設、携帯電話契約など、日本での生活立ち上げをサポートします。
- オンライン日本語教育: 業務に必要な日本語能力を向上させるための学習機会を提供します。
- 文化理解促進: 日本の文化や習慣、職場のルールなどを丁寧に伝え、相互理解を深めます。
- 相談体制の構築: 外国人材が困ったときに気軽に相談できる窓口を設けます。
「言葉の壁」は、コミュニケーション不足や安全トラブルに繋がる可能性があります。例えば、現場監督の「待って」という指示が「OK」と誤解され、施工ミスや転倒事故につながった事例も報告されています。このようなトラブルを予防するためには、
多言語マニュアルの整備や
動画を活用した作業指示、ジェスチャーの活用などが有効です。
日本人従業員との円滑なコミュニケーションを促すためには、異文化理解研修の実施や、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)でのペアリングなども効果的です。
まとめ

建設業の人手不足は待ったなしの状況です。外国人材の活用は、貴社の未来を拓く重要な一手となるでしょう。しかし、特定技能のなかで、建設分野のみ必要な手続きもあるため、外国人採用をする場合には十分に注意しましょう。不安なことがありましたら、専門の会社に相談することをおすすめいたします。
執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平
監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志
株式会社USEN WORKING所属。特定技能制度が創設された2019年の当初から、一貫して外国人採用の最前線に携わる。これまで、外国人の採用コンサルタントとして、介護・外食分野を中心に数多くの企業を支援。