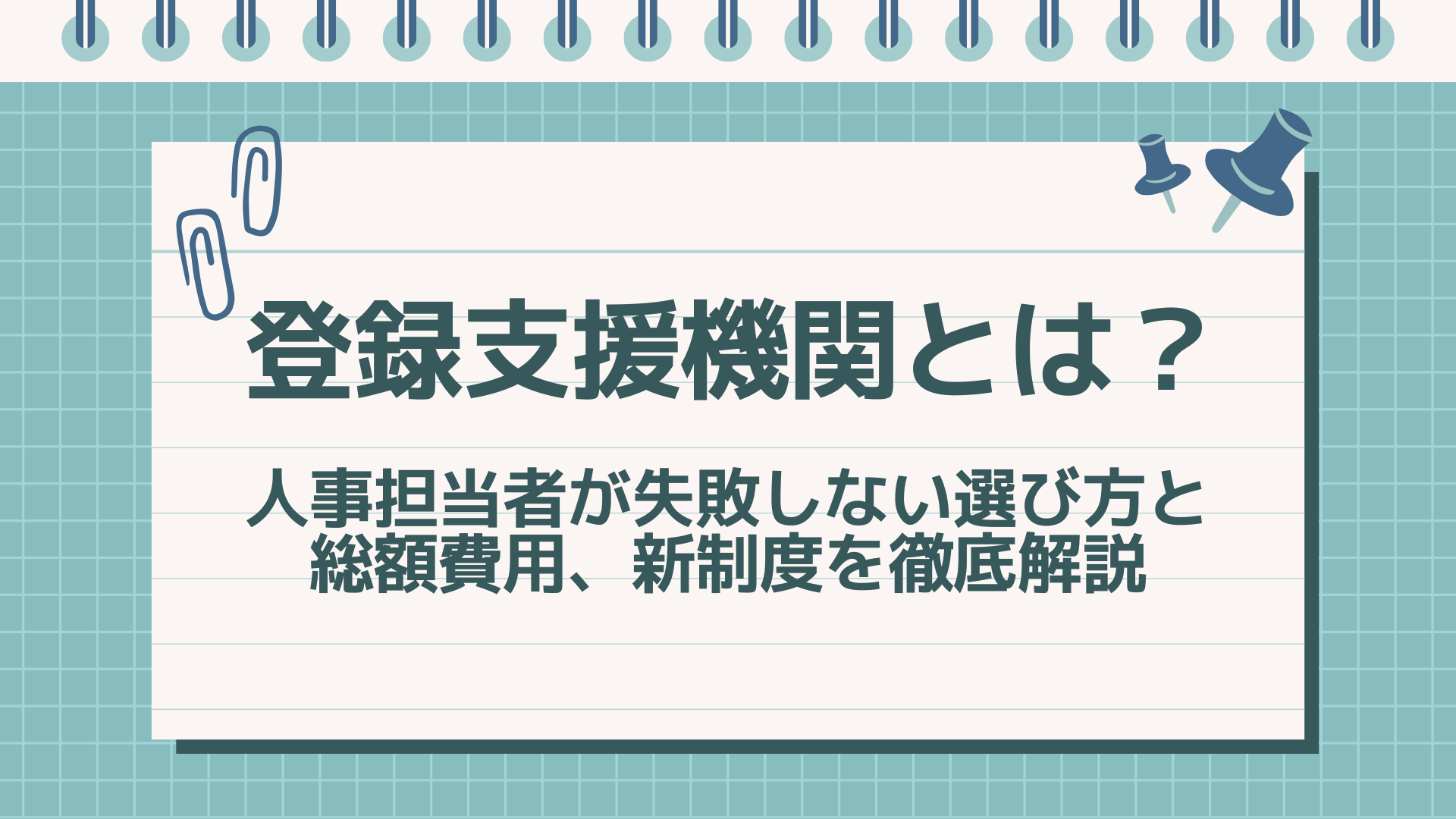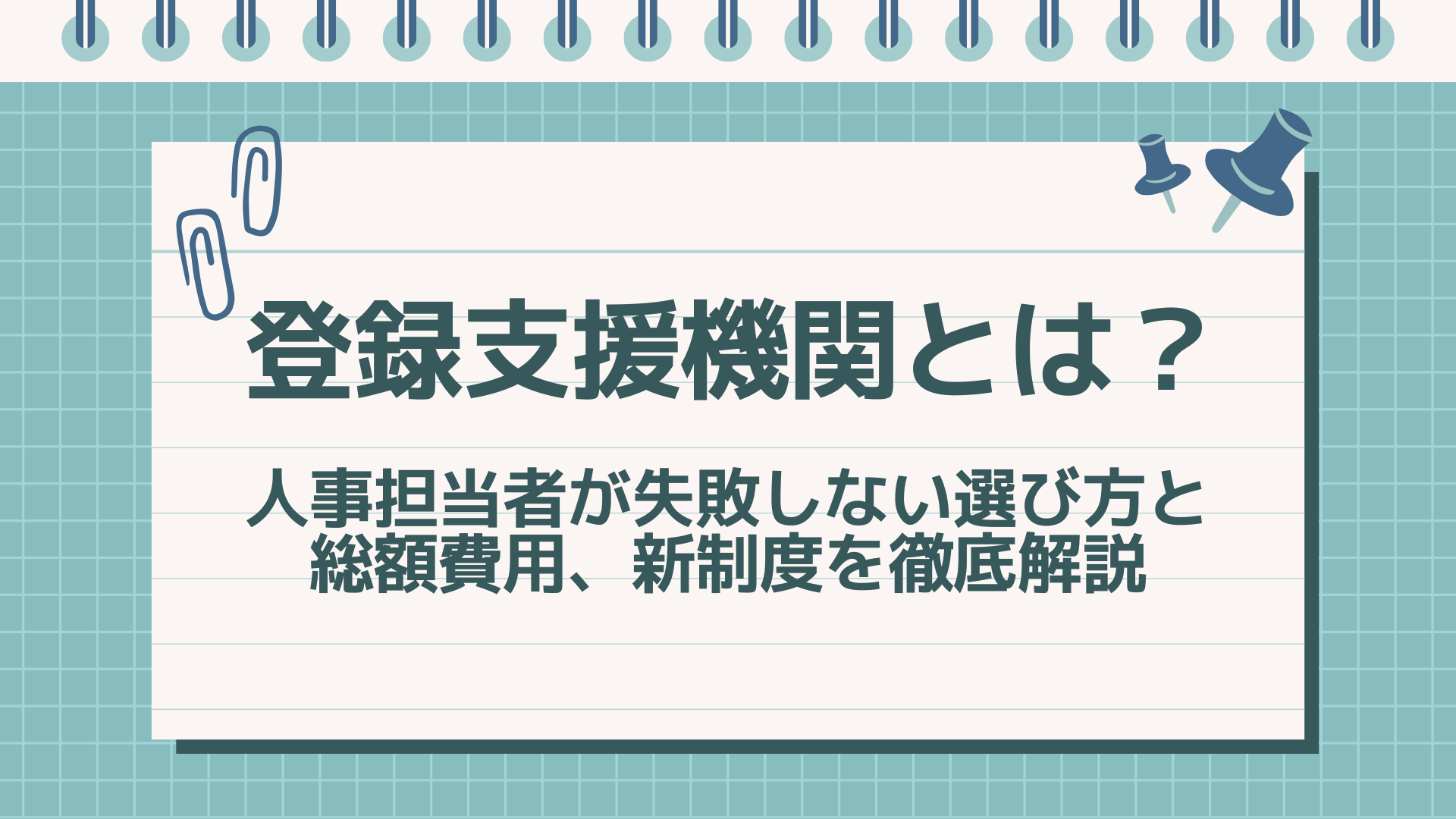
「登録支援機関」という言葉を耳にしても、「結局何をしてくれるの?」「費用はどれくらい?」「トラブルが起きたらどうしよう…」と、漠然とした不安と疑問で、なかなか次の一歩を踏み出せない人事担当者様も多いのではないでしょうか。
本記事では、まさに今、多くの人事担当者様が抱えるその不安を全て解消します。2024年に成立・公布された「育成就労」制度など、2025年以降の最新法改正に完全対応し、登録支援機関の定義から、人材紹介会社との違い、具体的な支援内容、そして最も気になる「総額費用」まで、外国人雇用未経験の担当者様でも「これならできる!」と自信を持てるよう、網羅的に解説します。
STAYWORKERは、これまで数多くの企業様の外国人材採用・定着を支援し、「現場で本当に役立つ実践的なノウハウ」を培ってきました。この記事を読み終える頃には、あなたにとって最適な登録支援機関を選び、外国人材と共に企業を成長させるための明確な「航海図」が手に入っているはずです。
目次

そもそも登録支援機関とは?初めての外国人雇用で知るべき基本
外国人材の雇用を検討する際、「登録支援機関」という言葉を耳にするものの、その役割や必要性について、まだ漠然としたイメージしかお持ちでない人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。まずは、その基本的な定義から見ていきましょう。
■定義と役割:特定技能外国人受け入れの「伴走者」
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)からの委託を受け、特定技能1号外国人が日本で安定して生活・就労できるよう、支援計画の作成から実施までを一貫して行う機関を指します。これは、出入国在留管理庁が定めている役割です。
特定技能外国人を雇用する企業には、法律で定められた支援を行う義務があります。しかし、異文化を持つ外国人材の生活をきめ細やかにサポートしたり、複雑な行政手続きを代行したりすることは、初めて外国人雇用を行う企業にとっては大きな負担となりかねません。そこで、この支援業務を専門的に担うのが登録支援機関なのです。
例えるなら、登録支援機関は、初めての海外旅行で不安な旅行者を、現地の言葉で道案内し、トラブルから守り、快適な旅をサポートする「現地ガイド」のような存在です。担当者は安心して本業に集中しながら、外国人材が日本で最大限の力を発揮できるよう、登録支援機関が「伴走者」としてきめ細やかなサポートを提供します。
■登録支援機関と「人材紹介会社」「監理団体」の決定的な違い
人事担当者様の中には、「人材紹介会社や監理団体と、登録支援機関は何が違うの?」と疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれません。特に「両方にお金を払うの?」という点は、ご不安に思われますよね。それぞれの役割は明確に異なります。
以下の表で、それぞれの機関の役割を比較してみましょう。

ご覧の通り、人材紹介会社は「採用」のフェーズ、登録支援機関は「採用後の支援」のフェーズをそれぞれ専門的に担います。監理団体は「技能実習制度」に特化した機関であり、特定技能制度とは異なる枠組みです。
したがって、特定技能外国人を雇用する際は、人材紹介会社を利用して人材を見つけ、その後の支援を登録支援機関に委託するというように、複数の機関と連携するケースが一般的です。もちろん、人材紹介から支援までを一貫して提供する機関もあります。
■自社支援と委託、どちらを選ぶべき?中小企業が考えるべき判断基準
特定技能外国人への支援は、必ずしも登録支援機関に委託しなければならないわけではありません。企業が自社で支援体制を構築する「自社支援」という選択肢もあります。
では、どちらの選択肢が最適なのでしょうか。
自社支援のメリット・デメリット
- メリット:
●コスト削減: 登録支援機関に支払う委託費用が発生しません。
●ノウハウ蓄積: 自社内に外国人雇用・支援のノウハウが蓄積されます。
●柔軟な対応: 支援内容や方法を自社の状況に合わせて柔軟に調整できます。
- デメリット:
●担当者の負担大: 支援業務は多岐にわたり、専門知識や多言語対応も求められるため、担当者の業務負担が非常に大きくなります。
●法的リスク: 支援計画の不備や支援義務の不履行は、在留資格の取り消しや企業の罰則に繋がりかねません。
●トラブル対応の難しさ: 外国人特有の生活習慣や文化の違いによるトラブル、緊急時の対応(病気、事故など)は、専門知識がないと解決が困難です。
登録支援機関への委託のメリット・デメリット
- メリット:
●専門性・安心感: 外国人雇用制度に精通した専門家が支援を行うため、法令順守のリスクを大幅に軽減できます。
●担当者の負担軽減: 煩雑な手続きや生活支援業務を任せられるため、貴社の人事担当者の負担が軽減され、本業に集中できます。
●トラブル対応力: 経験豊富な機関は、外国人材とのコミュニケーションやトラブル解決に長けています。
- デメリット:
●費用発生: 委託費用が発生します。
特に中小企業の場合、専任の人事担当者がいない、あるいは他の業務と兼任しているケースも多いでしょう。多言語対応ができる社員がいない、外国人材の生活習慣や文化について知識がないといった状況であれば、自社支援は非常にハードルが高く、かえってトラブルや離職に繋がり、結果的に大きなコストとなるリスクがあります。
自社支援を選ぶ際には、以下の体制が整っているか、いま一度ご確認ください。
- 専門知識を持つ担当者: 外国人雇用に関する最新の法令や支援内容を正確に理解し、常に情報更新できる担当者がいるか。
- 多言語対応: 外国人材の母国語に対応できるスタッフ、または通訳を確保できる体制があるか。
- 緊急時の対応力: 病気や事故、人間関係のトラブルなど、緊急時に迅速かつ適切に対応できる体制があるか。
これらの準備が難しいと感じるようであれば、専門家である登録支援機関への委託を強くおすすめします。

【2025年完全対応】外国人雇用が変わる!最新法改正が登録支援機関に与える影響
外国人材の受け入れ制度は、日本の社会情勢や国際情勢に合わせて常に変化しています。特に2024年に成立・公布された法改正は、今後の外国人雇用に大きな影響を与えるものです。古い情報に基づいた判断は、貴社にとって大きなリスクとなりかねません。ここでは、2025年以降の最新情報と、それが登録支援機関の役割にどう影響するかを解説します。
■新制度「育成就労」と特定技能のシームレスな連携とは?
2024年6月に成立した改正入管法により、従来の「技能実習制度」に代わる新制度として「育成就労」制度が創設されました(2027年までの導入を目指しています)。この育成就労制度は、3年間で特定技能1号レベルの人材を育成することを目的としており、特定技能への移行を前提とした、より計画的でシームレスな人材育成・活用を目指すものです。
これにより、登録支援機関の役割は、もはや特定技能外国人の生活支援に留まりません。育成就労の段階から特定技能への移行までを見据え、外国人材のキャリアパス形成を一貫して支援するという、より高度で戦略的な役割が求められるようになります。例えば、「育成就労計画」と連動した支援の具体的内容を策定し、外国人材がスムーズに特定技能へ移行できるよう伴走することが重要です。
STAYWORKERでは、この新しい制度体系の変化をいち早く捉え、育成就労段階から特定技能への移行まで、貴社と外国人材が安心して進めるよう、最適な支援体制を構築しています。長期的な視点で外国人材の活用を考えている企業様にとって、これは極めて価値の高い情報となるでしょう。
⇒
STAYWORKERの支援活動を見る
■特定技能の対象分野追加(自動車運送業、鉄道など)がもたらすチャンス
特定技能制度は、人手不足が深刻な分野で外国人材の受け入れを可能にする制度ですが、2024年以降、その対象分野がさらに拡大されました。具体的には、以下の4分野が新たに追加されています。
これにより、これらの業界に属する多くの企業様が、初めて外国人雇用を検討し始める「新規参入者」となる可能性があります。彼らはまさに今、最も正確で実践的な情報を渇望している層でありながら、市場にはまだ十分な専門情報が少ない状況ですし、新たな人材獲得のチャンスが広がっています。
■登録支援機関への「全委託義務化」と規制強化の動き
改正法により、特定技能外国人への支援を全て委託する場合、その委託先は**「登録支援機関」でなければならない**ことが明確化されました(2025年7月現在)。これは、これまで一部で存在していた「グレーゾーン」な委託のあり方を是正し、外国人材の保護と制度の適正な運用をより強化するための措置です。
この変更は、企業が登録支援機関を選定する上で極めて重要な前提条件となります。委託先が正式な登録支援機関であるかどうかを必ず確認し、法令を遵守した形で支援体制を構築する必要があります。
また、今後、登録支援機関に対する監督強化策(例:パフォーマンスに基づくランク付け評価案など)が導入されることも検討されています。これらの動きは、登録支援機関の質を向上させ、外国人材が安心して働ける環境をさらに整備することを目的としています。 外国人材を長期的に雇用し、成功させるためには、目先のコストだけでなく、5年後、10年後も付き合える信頼性の高いパートナーをいかに選ぶかが、これまで以上に重要になります。

登録支援機関の費用は総額いくら?隠れたコストと費用対効果を徹底解説
ここでは、特定技能外国人材の採用から雇用1年目までにかかる「総額費用」を具体的に解説し、経営層への説明にも役立つ情報を提供します。
■月額費用だけでは見えない!総額費用の内訳とシミュレーション
登録支援機関に支払う月額の支援委託料は、あくまで費用の一部に過ぎません。特定技能外国人材の採用から定着までには、以下のような様々な費用が発生します。
特定技能外国人材の採用から雇用1年目までにかかる総コストの内訳(モデルケース)
- 人材紹介料: 採用が決定した際に人材紹介会社に支払う費用です。
●目安:外国人材の年収の20%〜30%程度(例:年収250万円の場合、50万円〜75万円)
- 登録支援機関の支援委託料: 月額で発生する支援費用です。
●目安:月額2万円〜4万円程度(例:月額3万円の場合、1年間で36万円)
- 在留資格の申請・更新費用: 行政書士などに依頼する場合の費用です。
●目安:1回あたり5万円〜15万円
- 海外からの渡航費: 外国人材の飛行機代や、日本での初期生活費(食費など)です。
●目安:10万円〜20万円
- 住居の初期費用: 敷金、礼金、仲介手数料、家具家電の購入費などです。
●目安:10万円〜30万円
- 入国後の健康診断費用:
●目安:1回あたり5千円〜1万円
- その他: 送迎費用、日本語教育費用、企業側での受け入れ準備費用など。
●目安:数万円〜
これらの費用を合計すると、特定技能外国人を1名雇用し、1年間にわたって支援を委託した場合の総費用は、概ね80万円〜150万円程度が目安となるでしょう(人材紹介会社を利用し、住居を企業が提供するケース)。この金額はあくまで目安であり、国籍、職種、支援内容、住居の有無などによって大きく変動します。
■費用を抑えつつ失敗しないための3つのポイント
「少しでも費用を抑えたい」というお気持ちはよく分かります。しかし、安価な登録支援機関を選ぶことには、義務的支援の怠慢やトラブル時の不備など、かえって大きなリスクが潜んでいます。「安かろう悪かろう」の罠に陥らないためにも、費用対効果で選ぶことが重要です。
以下の3つのポイントで、コストと質のバランスを見極めましょう。
- 支援内容の具体性: 「何でもやります」という曖昧な説明ではなく、10項目の義務的支援以外に、どのような追加支援(日本語教育、キャリア相談、日本人従業員向け異文化理解研修な ど)がどこまで含まれるのかを具体的に確認しましょう。追加費用が発生するのかどうかも重要です。
- トラブル対応の実績と体制: 緊急時の連絡体制(24時間対応か、多言語対応か)や、過去にどのようなトラブルを、どのように解決に導いたかの事例を聞いてみましょう。トラブル発生時の対応力が、外国人材の定着に直結します。
- 定着支援へのコミットメント: 人材を紹介して終わり、手続きを代行して終わり、という機関では、外国人材の定着は難しいでしょう。採用して終わりではなく、入社後の定期面談の質、キャリアパス支援、職場での人間関係のフォローなど、長期的な定着に向けた具体的な取り組みについて確認することが重要です。
これらの点を総合的に判断することで、費用を抑えつつも、外国人雇用を成功に導く信頼できるパートナーを見つけることができるはずです。
[内部リンク推奨:外国人材の定着率を上げるには?企業が取り組むべき5つの施策]

失敗しない!良い登録支援機関の「見極め方」と「選び方」の全知識
「正直、『良い登録支援機関』と『悪い登録支援機関』の見分けがつかない」――多くの人事担当者様が抱えるこの不安を解消するため、ここでは信頼できる登録支援機関を見極めるための具体的なチェックリストと、よくあるトラブル事例から学ぶ回避策をご紹介します。
■悪質な登録支援機関に騙されないためのチェックリスト
残念ながら、登録支援機関の数が乱立している現状では、中には質の低い機関も存在します。貴社が「安かろう悪かろう」の罠に騙されないためにも、以下のチェックリストを活用し、慎重に選定を進めましょう。
- 支援実績の透明性:
●これまでの支援人数、受け入れ企業の業種、外国人材の定着率など、具体的なデータを開示しているか?
●具体的な導入事例やお客様の声が豊富にあるか?
- 契約内容の明確さ:
●支援内容(10項目の義務的支援に加えて、どのような支援が含まれるか)が契約書に具体的に明記されているか?
●費用体系(月額費用、初期費用、その他諸経費)が明確で、後から追加費用が発生しないか?
●トラブル発生時の対応(連絡体制、費用負担など)が明確に記載されているか?
- 担当者の専門性・対応力:
●担当者が外国人材制度や関係法令に精通しているか?
●外国人材の母国語に対応できるスタッフがいるか?
●問い合わせに対するレスポンスは迅速か、丁寧か?
●面談時に貴社の状況や課題をしっかりヒアリングし、具体的な提案をしてくれるか?
- 支援体制の具体性:
●定期面談の頻度と内容が具体的に定められているか?(単なる形式的な面談ではないか)
●外国人材の住居確保や公共料金の手続きなど、生活支援の具体的な - フローが確立されているか?
●緊急時の24時間対応や、休日・夜間の連絡体制が整っているか?
評判・口コミ:
●既存の受け入れ企業からの評価や口コミはどうか?(可能であれば直接話を聞く機会を設けてもらう)
●過去に行政指導や登録取り消しなどの処分を受けていないか?(出入国在留管理庁のウェブサイトで確認可能)
●登録支援機関に関する最新の規制強化や監督強化策については、出入国在留管理庁のウェブサイトなどで、常に最新の情報を確認することをお勧めします。-
■トラブル事例から学ぶ!登録支援機関との連携で起こりがちな問題と回避策
外国人雇用においては、予期せぬトラブルが発生することもあります。ここでは、登録支援機関との連携で起こりがちな具体的なトラブル事例とその回避策をご紹介します。
- 事例1: 支援義務の不履行
●問題: 月額費用が安いことを謳う登録支援機関に委託したものの、義務的支援の一部を怠ったり、形だけの支援しか行わなかったりするケース。これにより、外国人材の生活が不安定になり、貴社が法令違反のリスクを負うことになります。
●回避策: 契約書で支援内容を具体的に明記し、定期的な支援報告を義務付けること。また、外国人材本人からも直接、支援が適切に行われているかを確認する機会を設けることが重要です。
- 事例2: 外国人材の失踪・離職時の対応不備
●問題: 外国人材が突然職場に来なくなり、登録支援機関に連絡しても「本人と連絡が取れない」「うちの責任ではない」と対応してくれないケース。貴社は、外国人材の行方が分からなくなり、法的な問題に直面する可能性があります。
●回避策: 定期面談の質が高く、外国人材との信頼関係を構築できている機関を選ぶこと。また、緊急時の連絡体制が24時間体制であるか、トラブル発生時にどのような対応を約束しているかを契約前に確認しましょう。
- 事例3: 職場での人間関係・文化摩擦への対応不足
●問題: 日本人従業員と外国人材の間で文化や習慣の違いから軋轢が生じたり、コミュニケーション不足による誤解が生じたりした際に、登録支援機関が適切な橋渡しをしてくれないケース。職場の雰囲気が悪化し、外国人材の定着にも悪影響を及ぼします。
●回避策: 事前ガイダンスや生活オリエンテーションが充実しているか、異文化理解に関する企業向けの研修を提供しているかを確認しましょう。単に手続きを代行するだけでなく、貴社と外国人材双方の文化理解を促進する支援を行える機関が理想的です。
[内部リンク推奨:
特定技能外国人受入れのトラブル事例3選!事前に防ぐ方法についても解説!]
■STAYWORKERが提供する「安心」の支援体制
STAYWORKERは、上記のチェックリストの項目を全てクリアし、貴社に「安心」と「成功」をお届けするための支援体制を構築しています。
- 豊富な支援実績と高い定着率: これまで数多くの特定技能外国人材の受け入れを支援し、**独自のきめ細やかな支援体制により、**98%という高い定着率を実現しています。この実績が、貴社の不安を解消する最も確かな証拠です。詳細な定着率データやお客様の具体的な声は、導入事例ページでご確認いただけます。
- 多言語対応可能な専門スタッフ: 外国人材の母国語に精通した専門スタッフが、きめ細やかなサポートを提供。言葉の壁による誤解やトラブルを未然に防ぎます。
- 入社後の徹底した伴走支援: 入社後の定期面談では、単なる形式的なヒアリングに留まらず、外国人材のキャリアパス相談や職場での人間関係の悩みにも深く踏み込みます。
- 緊急時の24時間対応体制: 万が一のトラブル時にも、24時間体制で迅速に対応。貴社と外国人材双方の不安を最小限に抑えます。
私たちSTAYWORKERは、単なる手続き代行業者ではありません。貴社の外国人雇用を成功に導く「伴走者」として、採用から定着まで、あらゆるフェーズで強力にサポートいたします。

STAYWORKERの実践知:登録支援機関の支援業務を「解像度高く」解説
特定技能制度において、登録支援機関には10項目の義務的支援が定められています。しかし、これらの項目は文字情報だけではその大変さや重要性が伝わりにくいものです。STAYWORKERでは、これまでの豊富な支援経験に基づき、これらの業務が「現場で本当に何を意味するのか」を、より解像度高く解説します。
■10項目の義務的支援を徹底解剖:現場で本当に必要なこととは?
法律で定められた10項目の支援業務は、外国人材が日本で安心して働き、生活を送るために不可欠です。STAYWORKERが、それぞれの業務においてどのような「実践的な支援」を行っているのか、その一部をご紹介します。
- 事前ガイダンス:
●一般的な説明: 雇用条件、活動内容、日本での生活に関する情報提供。
●STAYWORKERの実践知: 就労前に、外国人材の母国語で、労働条件や生活習慣、日本のルールについて、具体的な事例を交えながら丁寧に説明します。例えば、ゴミの分別方法、近隣住民との付き合い方、交通ルールなど、日本人が当たり前と思っていることでも、外国人材にとっては初めてのことばかりです。これにより、入国後のギャップを最小限に抑え、トラブルを未然に防ぎます。
- 出入国時の送迎:
●一般的な説明: 空港などへの送迎。
●STAYWORKERの実践知: 入国時は、長時間のフライトで疲れている外国人材を、空港の到着ロビーで確実に出迎え、宿泊先まで安全に誘導します。単なる送迎ではなく、異国の地での最初の「安心」を提供することに重きを置いています。帰国時も同様に、最後まで責任を持ってサポートします。
- 住居確保の支援:
●一般的な説明: 物件探しや契約手続きのサポート。
●STAYWORKERの実践知: 外国人材が安心して生活できる住居の確保を支援します。賃貸契約には保証人が必要となるケースも多く、外国人材が単独で契約することは困難です。STAYWORKERでは、連帯保証人代行サービスの紹介や、提携不動産会社との連携により、スムーズな住居探しをサポートします。
- 生活オリエンテーション:
●一般的な説明: 日本の生活ルール、交通、医療などに関する情報提供。
●STAYWORKERの実践知: 入国後、市区町村役場での住民登録、国民健康保険への加入、銀行口座の開設、携帯電話の契約といった、生活に必要な初期手続きに同行し、通訳を介して詳細を説明します。例えば、A市役所の市民課窓口で住民登録を行い、次に税務課で課税証明書を取得。その後、B銀行の窓口で口座を開設。全体で約4時間。この際、本人確認書類の不備や専門用語の誤解といったトラブルが頻発するため、母国語対応可能な支援担当者の同行がなければ、1日がかりの作業になることも珍しくありません。
- 公的手続きへの同行:
●一般的な説明: 役所での手続きへの同行。
●STAYWORKERの実践知: 上記の生活オリエンテーションで触れた手続きに加え、必要に応じて、税金や年金、その他行政サービスに関する手続きにも同行し、複雑な書類作成や専門用語の翻訳をサポートします。
- 日本語学習の機会提供:
●一般的な説明: 日本語学習方法に関する情報提供。
●STAYWORKERの実践知: 外国人材の日本語レベルや希望に応じ、地域の日本語教室やオンライン学習サービスの紹介、学習教材の提供を行います。職場でのコミュニケーションが円滑になるよう、実用的な日本語学習を促します。
- 相談・苦情への対応:
●一般的な説明: 職場や生活上の相談対応。
●STAYWORKERの実践知: 外国人材からの相談や苦情に、母国語で24時間体制で対応します。単に話を聞くだけでなく、問題の本質を見極め、企業と連携しながら具体的な解決策を提示します。例えば、日本人従業員との連携ミスや給与への不満からの退職といった、企業が最も恐れるリアルな問題に対し、STAYWORKERが過去にどのように介入し、解決に導いたかの匿名化されたミニケーススタディもございます。
- 日本人との交流促進:
●一般的な説明: 生活や仕事に関する情報提供。
●STAYWORKERの実践知: 災害時の避難情報、地域のイベント情報、生活に役立つ行政サービスなど、外国人材のニーズに合わせた最新の情報を定期的に提供します。
- 転職支援(解雇等発生時):
●一般的な説明: 解雇や自己都合退職の場合の転職先探しのサポート。
●STAYWORKERの実践知: 万が一、外国人材が解雇されたり、自己都合で退職を希望したりした場合でも、新たな特定技能所属機関の紹介や、在留資格変更手続きのサポートを行い、外国人材の日本での継続的な就労を支援します。
- 定期的な面談:
●一般的な説明: 定期的な面談。
●STAYWORKERの実践知: 3ヶ月に1回以上、企業担当者様と外国人材双方と面談を実施します。この面談は、単なるヒアリングではありません。外国人材の生活状況や健康状態、職場での人間関係、キャリアに関する相談まで深く踏み込み、離職の兆候を早期に発見し、定着率を高めるための重要な経営活動と位置付けています。
まとめ:外国人雇用で成功するために
本記事では、「登録支援機関とは何か」という基本的な疑問から、2025年の最新法改正、気になる費用総額、そして失敗しない登録支援機関の選び方まで、外国人雇用を検討する人事担当者様が知るべき情報を網羅的に解説しました。
登録支援機関は、特定技能外国人を安全かつ成功裏に雇用し、定着させるための「信頼できる伴走者」です。特に、2025年以降は「育成就労」制度との連携や、登録支援機関への「全委託義務化」など、制度が大きく変化していきます。この変化の波を乗りこなし、外国人材を貴社の成長の原動力とするためには、最新の知識と、現場の実践知に裏打ちされた支援力を持つパートナーを選ぶことが不可欠です。
STAYWORKERは、豊富な経験と高い定着率の実績を持ち、貴社の外国人雇用を強力にサポートできる体制を整えています。人手不足の解消はもちろん、外国人材が貴社の未来を支える「コア人材」として活躍できるよう、私たちSTAYWORKERが全力で伴走いたします。
貴社が外国人雇用で成功するための「航海図」を、ぜひSTAYWORKERと共に手に入れてください。