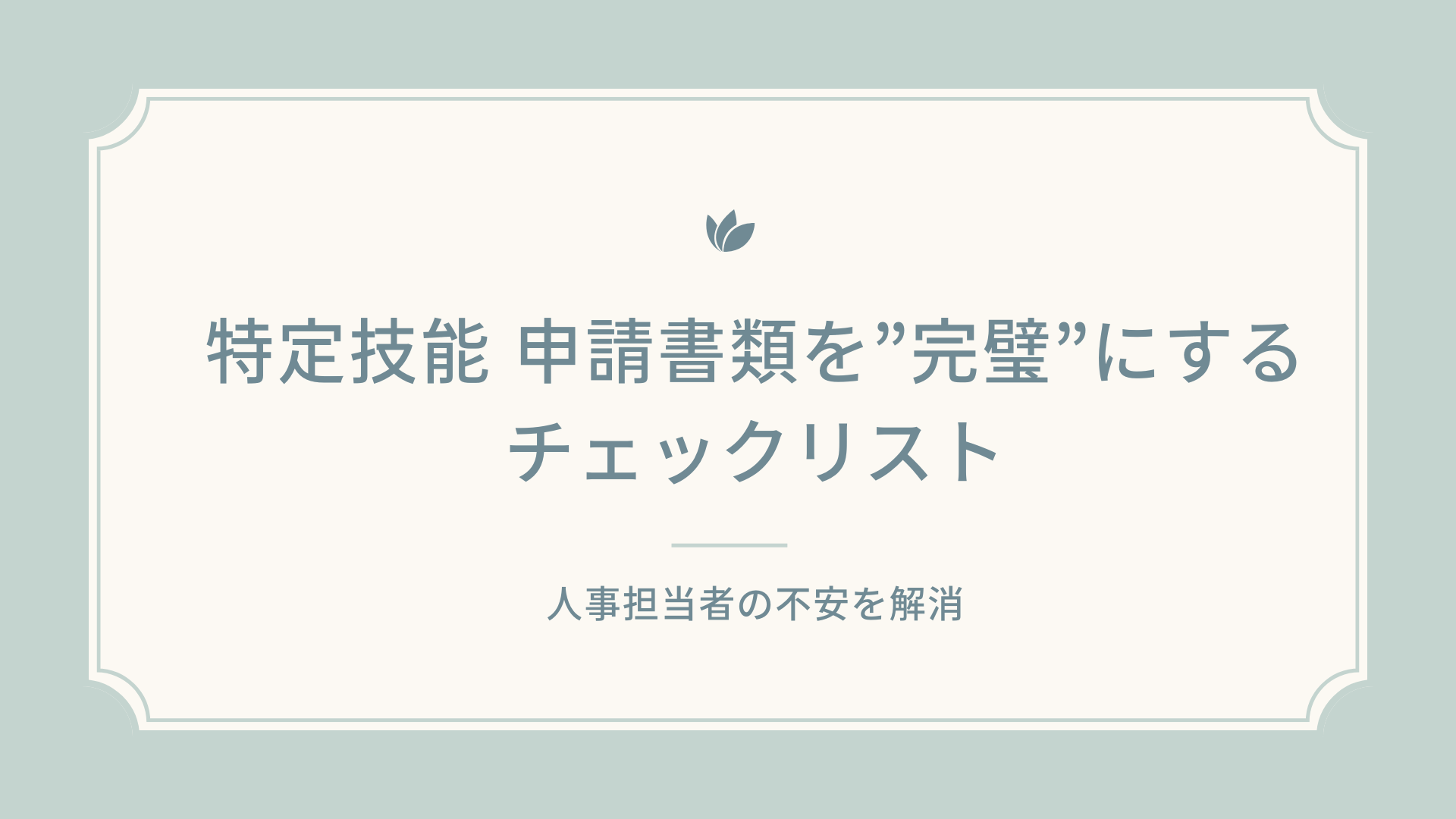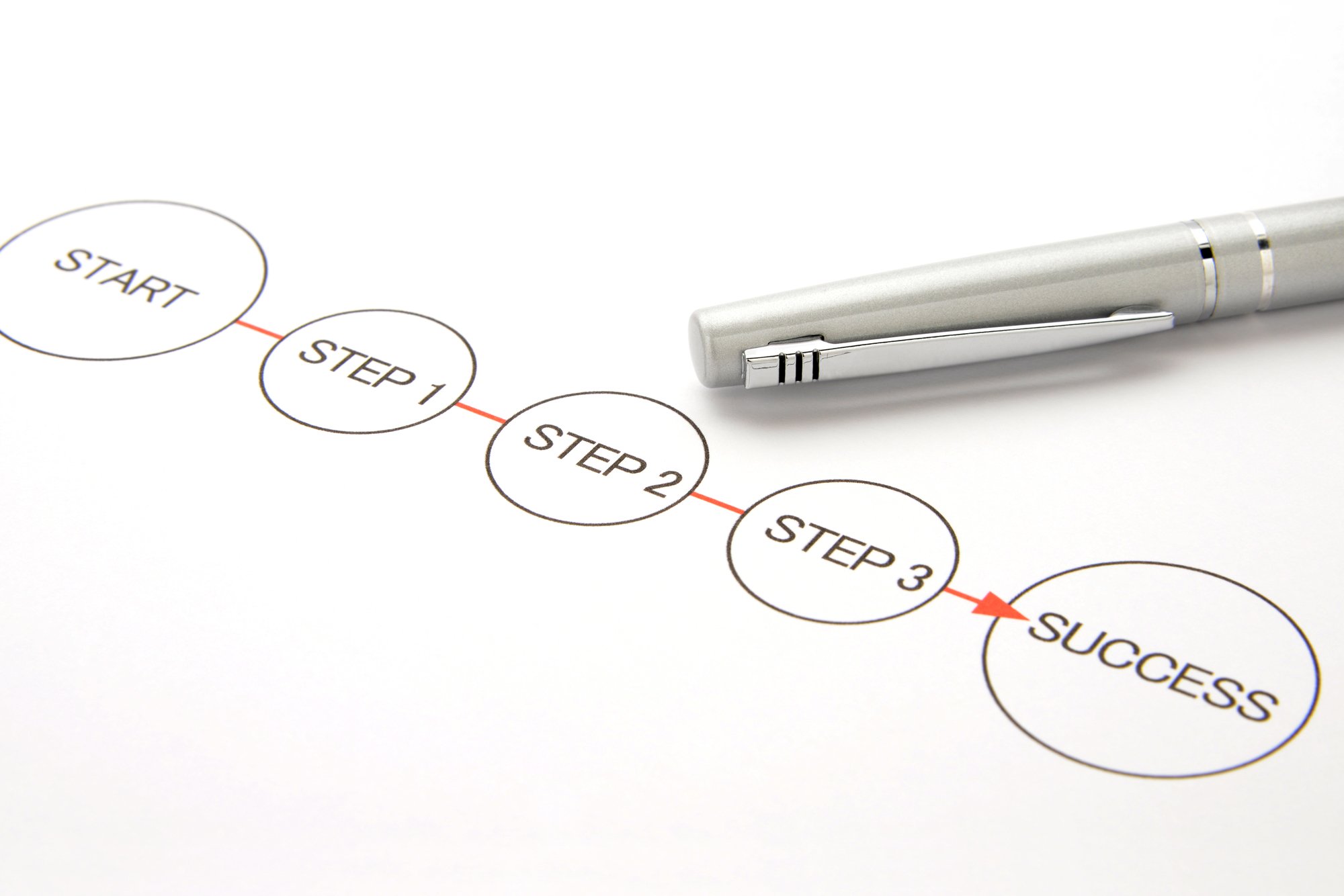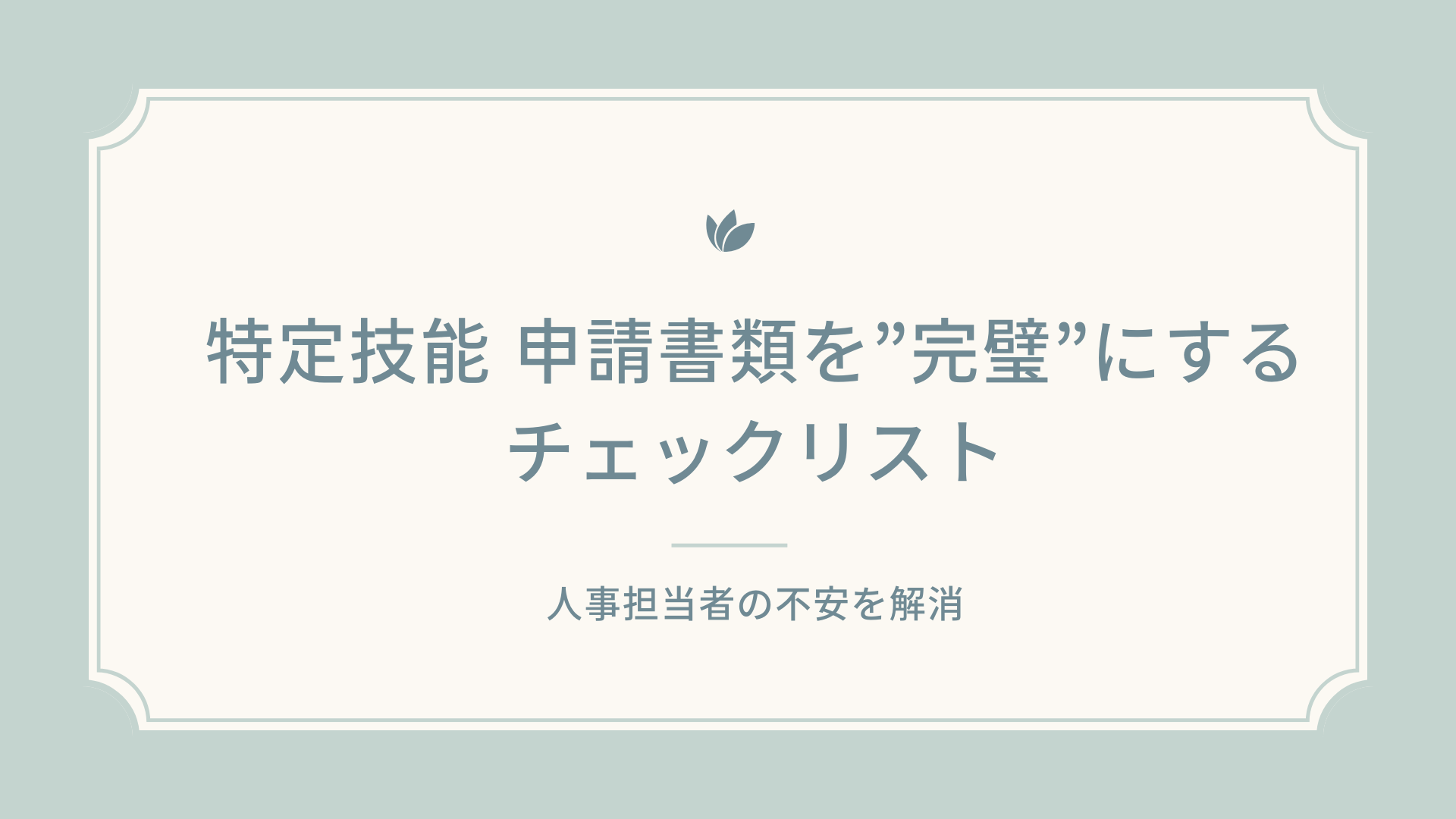
「特定技能外国人の採用を検討しているものの、『膨大な申請書類の準備に、何から手をつけていいか分からない』『不備で差し戻しになったらどうしよう』と、その複雑さに頭を抱えていませんか? 人手不足解消を前に、書類手続きの壁に直面し、時間ばかりが過ぎていく焦りを感じているかもしれません。」
本記事では、特定技能申請に必要な書類の全リストから、正確な書き方、そして最も恐れる「不備による差し戻し」を避けるための具体的な対策まで、初めての方でも迷わず進められるよう徹底解説します。この記事を読み終える頃には、貴社は煩雑な手続きから解放され、スムーズかつ確実に外国人材の採用を実現するための具体的な道筋が見えているはずです。
STAYWORKERは、法務省・出入国在留管理庁の公開情報を基盤としつつ、数多くの企業様の外国人材採用を支援してきた豊富な実務経験に基づき、実践的で信頼性の高い情報をお届けします。
目次
特定技能申請の全体像を理解する:なぜ書類が「複雑」なのか?

特定技能制度は、深刻な人手不足に直面している産業分野において、外国人材を即戦力として受け入れるために創設されました。この制度の目的は、単に労働力を確保するだけでなく、外国人材の生活や就労を適切に保護し、安定した日本での活動を保障することにもあります。
そのため、申請書類は単なる労働ビザの申請とは異なり、企業(受入れ機関)と外国人材双方に課せられる義務と責任を明確にするための多岐にわたる資料が求められます。
「なぜこんなに書類が多いのだろう」「何から手をつければいいのか」と、その複雑さに頭を抱える担当者様も多いのではないでしょうか。この「複雑さ」の背景には、主に以下の3つの要因があります。
- 法務省・出入国在留管理庁の膨大な情報: 公式サイトには詳細な情報が掲載されていますが、その量は膨大で、どこに何が書かれているかを見つけるだけでも一苦労です。
- 頻繁な様式変更: 特定技能制度は比較的新しい制度であり、運用要領や提出書類の様式が頻繁に更新されます。例えば、2025年8月1日、7月1日、6月1日といった日付で改定が行われることも珍しくありません。古い様式で提出してしまうと、不備となり申請が差し戻されるリスクがあります。
- 専門用語の多さ: 法律や行政手続きに関する専門用語が多く、初めて外国人材の採用を担当する方には理解が難しい場合があります。
特定技能の申請書類は、まるで初めて挑む巨大なパズルのピース集めのようなものです。一つでもピースが欠けたり、形が違えば完成しない。しかし、正しい手順とガイドがあれば必ず完成できます。本記事が、貴社のパズルを完成させるための確かなガイドとなることを目指します。
特定技能制度とは?(制度全般に関する詳細記事へ)
特定技能の対象分野一覧(各分野の詳細記事へ)
【状況別】特定技能申請の「必要書類」完全チェックリスト

特定技能の申請に必要な書類は、外国人材が「海外から新規で日本に招へいされるのか」または「既に日本に在留しているのか」によって大きく異なります。ここでは、それぞれの状況に応じた必要書類と、すべての申請で共通して重要となる書類について解説します。
■【海外から新規招へい】在留資格認定証明書交付申請の必要書類
海外から特定技能外国人材を招へいする場合、「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。主な必要書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書: 所定の様式をダウンロードして使用します。
- 技能試験・日本語試験合格証明書: 外国人材が特定技能の各分野で求められる技能水準と日本語能力水準を満たしていることを証明します。有効期限内のものが必要です。
- 健康診断個人票: 申請日から遡り3ヶ月以内に医師の診断を受けたものが必要です。
- 写真(縦4cm×横3cm): 3ヶ月以内に撮影したものを指定の規格で用意します。
- その他、分野ごとの書類: 外食業分野技能測定試験合格証明書など、特定産業分野ごとに異なる書類が必要です。
※最新の必要書類リストは、必ず法務省・出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
■【国内在留者】在留資格変更許可申請の必要書類
既に日本に在留している外国人材(例:留学ビザ、技能実習ビザなど)を特定技能に変更する場合、「在留資格変更許可申請」が必要となります。主な必要書類は以下の通りです。
- 在留資格変更許可申請書: 在留期間更新許可申請書とは様式が異なるため注意が必要です。
- 申請人のパスポート・在留カードの提示: 原本提示が必須です。
- 特定技能雇用契約書の写し: 業務内容、報酬額、支援内容の記載に不備がないか要確認です。
- その他、技能試験・日本語試験合格証明書、健康診断個人票など: 海外からの招へい時と同様に必要となります。
特に、現有ビザでの活動内容と特定技能の整合性が問われる場合がありますので、専門家への相談もご検討ください。
※最新の必要書類リストは、必ず法務省・出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
■【共通】すべての申請で必要な重要書類と取得ポイント
上記のいずれの申請においても共通して重要となる書類があります。これらは、特定技能制度の適正な運用を担保するために特に重視される書類です。
- 受入れ機関の概要書:企業の事業内容や財務状況などを説明する書類です。提出書類の省略条件に該当しない場合に必要となります。
- 1号特定技能外国人支援計画書: 特定技能外国人材が日本で安定して生活・就労できるよう、企業がどのような支援を行うかを具体的に示す計画書です。支援内容が適切に記載され、企業が実行可能であることが重要です。
- 特定技能雇用契約書の写し: 外国人材との雇用契約内容を明記した書類です。業務内容、報酬額、労働時間などが、日本人と同等以上であることや、他の書類との整合性が求められます。
- 報酬に関する説明書: 雇用契約書に記載された報酬額の根拠などを説明する書類です。
【重要】省略できる書類について:
上場企業や、過去3年間に指導助言・改善命令を受けていない企業など、特定の条件を満たす所属機関(受入れ企業)については、10項目もの提出書類が省略できる場合があります。これは申請プロセスを大幅に簡略化できる大きなメリットです。貴社が該当するかどうか、必ず確認しましょう。
※書類省略の最新条件は、必ず法務省・出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
書類作成で「失敗しない」ための具体的な書き方と注意点

特定技能の申請書類は、ただ揃えれば良いというものではありません。正確な情報と適切な記載が求められます。ここでは、書類作成時に陥りやすいミスを防ぎ、スムーズな申請を実現するためのポイントを解説します。
■申請書・添付書類の基本ルールと記入例
特定技能の申請書様式は、法務省の公式サイトからダウンロードできます。
※最新の様式と記載例は、必ず法務省・出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
ダウンロードした様式は、記載要領をよく読み込み、記入例を参考にしながら正確に記入することが重要です。些細な記載ミスでも、書類不備として差し戻され、審査期間が大幅に遅れる原因となります。例えば、氏名の漢字表記とローマ字表記の不一致、生年月日や住所の誤記など、基本的な情報こそ慎重に確認しましょう。
■特に注意すべき「雇用契約書」と「支援計画書」のポイント
特定技能の申請において、特に重要度が高く、不備が発生しやすいのが「特定技能雇用契約書」と「1号特定技能外国人支援計画書」です。
- 雇用契約書:
- 報酬額の整合性: 雇用契約書に記載された報酬額が、報酬に関する説明書や他の関連書類と一致しているか、必ず確認してください。雇用契約書と報酬に関する説明書に記載された報酬額が一致しないといった、ごく初歩的な書類不備によって申請が差し戻されるケースが頻繁に発生しています。
- 労働条件の明示: 日本人労働者と同等以上の報酬額であること、労働時間、休日、休暇などが明確に記載されている必要があります。
- 支援計画書:
義務的支援項目の網羅性: 事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応、行政機関への情報提供など、特定技能制度で定められた義務的支援項目がすべて盛り込まれているか確認しましょう。-
実行可能性: 計画書に記載された支援内容が、実際に実行可能であるかどうかが重要です。机上の空論ではなく、具体的な実施体制や担当者を明記することで、信憑性が高まります。
これらの書類は、外国人材の保護と制度の適正な運用に直結するため、出入国在留管理庁の審査でも特に厳しくチェックされます。
■ 情報の鮮度を保つ「最新版」確認の重要性
特定技能制度は、社会情勢や運用状況に合わせて頻繁に更新される「動的な制度」です。2025年最新版の情報を掲載していますが、運用要領や様式が頻繁に更新されています。
そのため、申請書類の準備に取り掛かる際は、必ず法務省の公式サイトの「更新履歴」を定期的に確認し、最新の様式を使用することが極めて重要です。古い様式や情報に基づいて作成された書類は、不備として扱われ、審査の遅延や不許可につながるリスクがあります。
特定技能申請で「よくある不備」とSTAYWORKERの解決策

特定技能の申請プロセスで、担当者様が最も恐れるのが「書類不備」による差し戻しではないでしょうか。たった一枚の書類の不備が、入社を数ヶ月遅らせることもあります。ここでは、よくある書類不備の具体例と、STAYWORKERがどのようにそのリスクを解決してきたかをご紹介します。
■ 書類不備が引き起こす「深刻な遅延」の現実
出入国在留管理庁の審査では、提出された書類が多岐にわたるため、わずかな不備でも審査が中断され、追加資料の提出や再申請を求められることがあります。これにより、外国人材の入国や就労が計画通りに進まないことがよくあります。特に、中小企業様では専任の法務部門を持たないことが多く、日常業務と並行して複雑な書類作成を行うため、不備が発生しやすい傾向にあります。
特定技能申請の具体的な「手続きの流れ」と期間
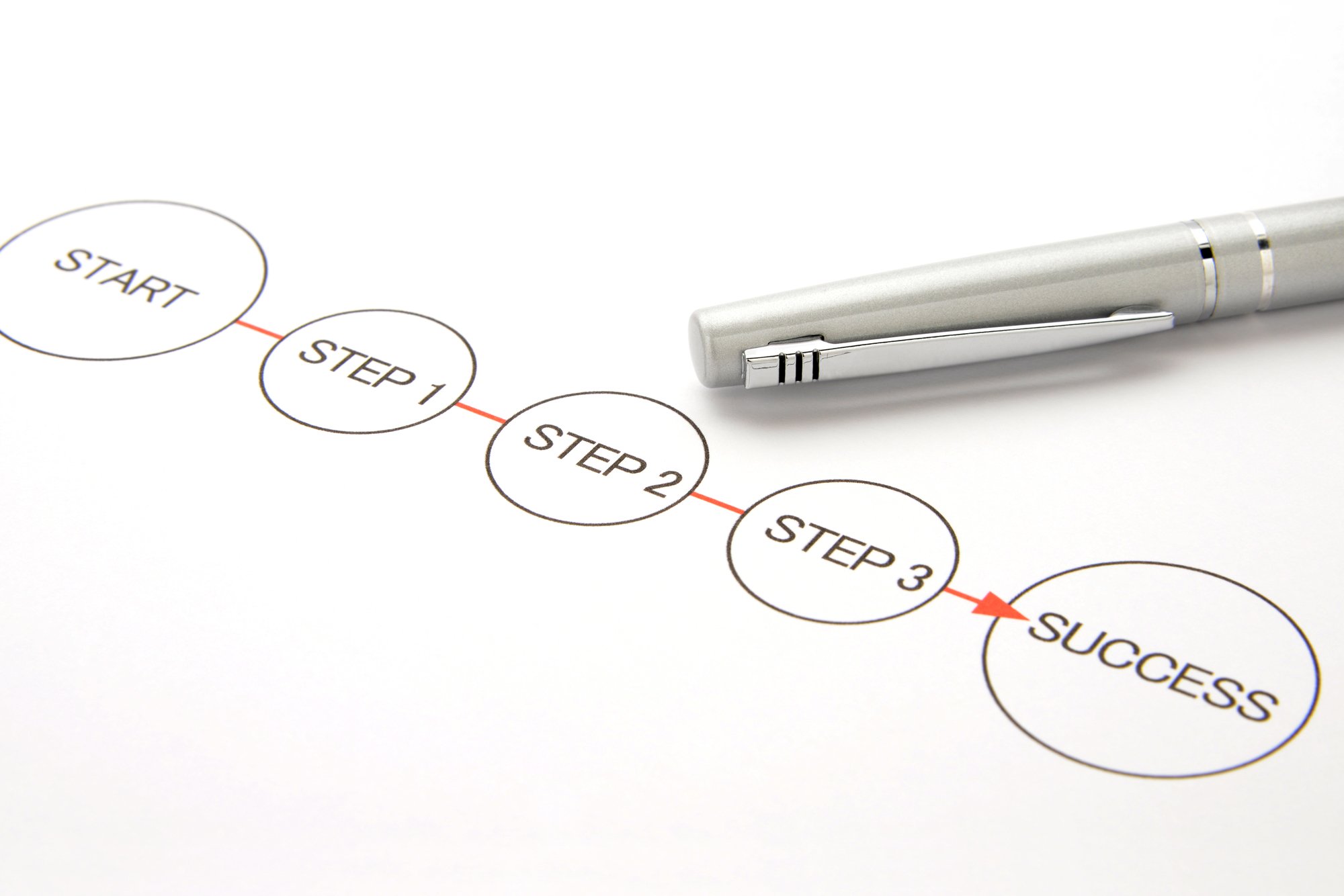
特定技能外国人材の採用から入国・就労開始までの手続きは、大きく以下のステップで進みます。全体の流れと期間を把握し、計画的に準備を進めることが重要です。
- 採用活動・候補者の決定: まずは外国人材の採用活動を行い、受け入れたい候補者を決定します。
- 必要書類の準備: 本記事で解説した各種申請書類を準備します。この段階が最も時間と労力を要します。
- 出入国在留管理庁への申請: 準備した書類を管轄の出入国在留管理庁へ提出します。
- 審査: 提出された書類に基づいて審査が行われます。
- 在留資格認定証明書交付/在留資格変更許可: 審査に通過すると、在留資格認定証明書が交付されるか、在留資格変更が許可されます。
- 査証(ビザ)申請・入国(海外からの招へいの場合): 在留資格認定証明書が交付されたら、外国人材が自国で査証(ビザ)申請を行い、日本へ入国します。
- 就労開始: 日本入国後、または在留資格変更許可後、特定技能外国人材は貴社での就労を開始します。
標準的な審査期間の目安は、在留資格認定証明書交付申請で1~3ヶ月、在留資格変更許可申請で2週間~2ヶ月程度(2025年7月現在の目安)ですが、申請内容や時期によって変動する可能性があります。余裕を持ったスケジュールを組み、早めに準備を開始することが成功の鍵です。
※最新の審査期間や手続きの詳細は、必ず出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
特定技能申請書類に関するよくある質問 (FAQ)
特定技能の申請書類に関する疑問は解消されましたでしょうか。最後に、よくある質問とその回答をまとめました。
■特定技能申請書類に関するFAQ
Q1. 特定技能申請に費用はかかりますか?(手数料の有無)
A1. 特定技能の在留資格申請自体に、出入国在留管理庁へ支払う手数料はかかりません。ただし、行政書士などの専門家へ代行を依頼する場合は、別途費用が発生します。
特定技能の費用(詳細記事へ)
Q2. 書類作成にどれくらいの期間がかかりますか?
A2. 貴社の状況や準備の進捗によりますが、必要書類の収集から作成まで、おおよそ1ヶ月から2ヶ月程度の期間を見込んでおくのが一般的です。特に初めての場合は、さらに余裕を持つことをおすすめします。
Q3. 申請が不許可になったらどうなりますか?
A3. 申請が不許可になった場合でも、再申請は可能です。不許可理由を確認し、不備を解消した上で再度申請を行います。
Q4. 登録支援機関は必ず必要ですか?
A4. 特定技能外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、外国人材への支援を行う義務があります。自社で支援体制を構築できない場合は、登録支援機関に支援計画の実施を委託する必要があります。
登録支援機関の役割(詳細記事へ)
■まとめ
特定技能の申請書類は複雑で、一つ一つの確認に時間と労力がかかります。貴社が抱える人手不足の課題をスムーズに解決するためにも、専門家のサポートをご検討ください。
執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平
監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志
株式会社USEN WORKINGの外国人採用コンサルタント。人材紹介・派遣の法人営業として多くの企業の採用課題に、そして飲食店経営者として現場のリアルに、長年向き合ってきた経験を持つ。採用のプロと経営者、双方の視点から生まれる具体的かつ実践的な提案を信条とし、2022年の入社以来、介護・外食分野を中心に数多くの企業の外国人採用を成功に導く。