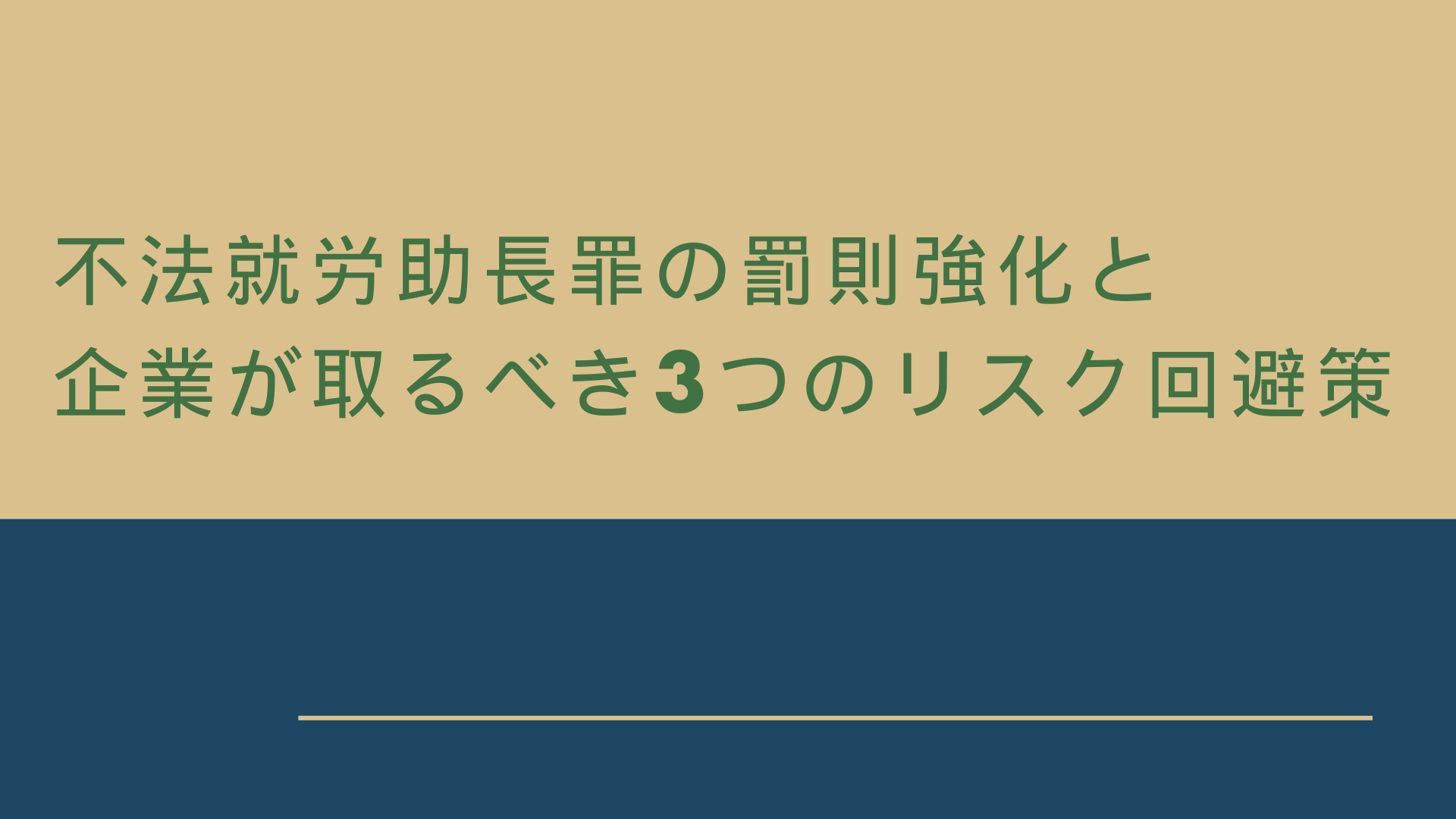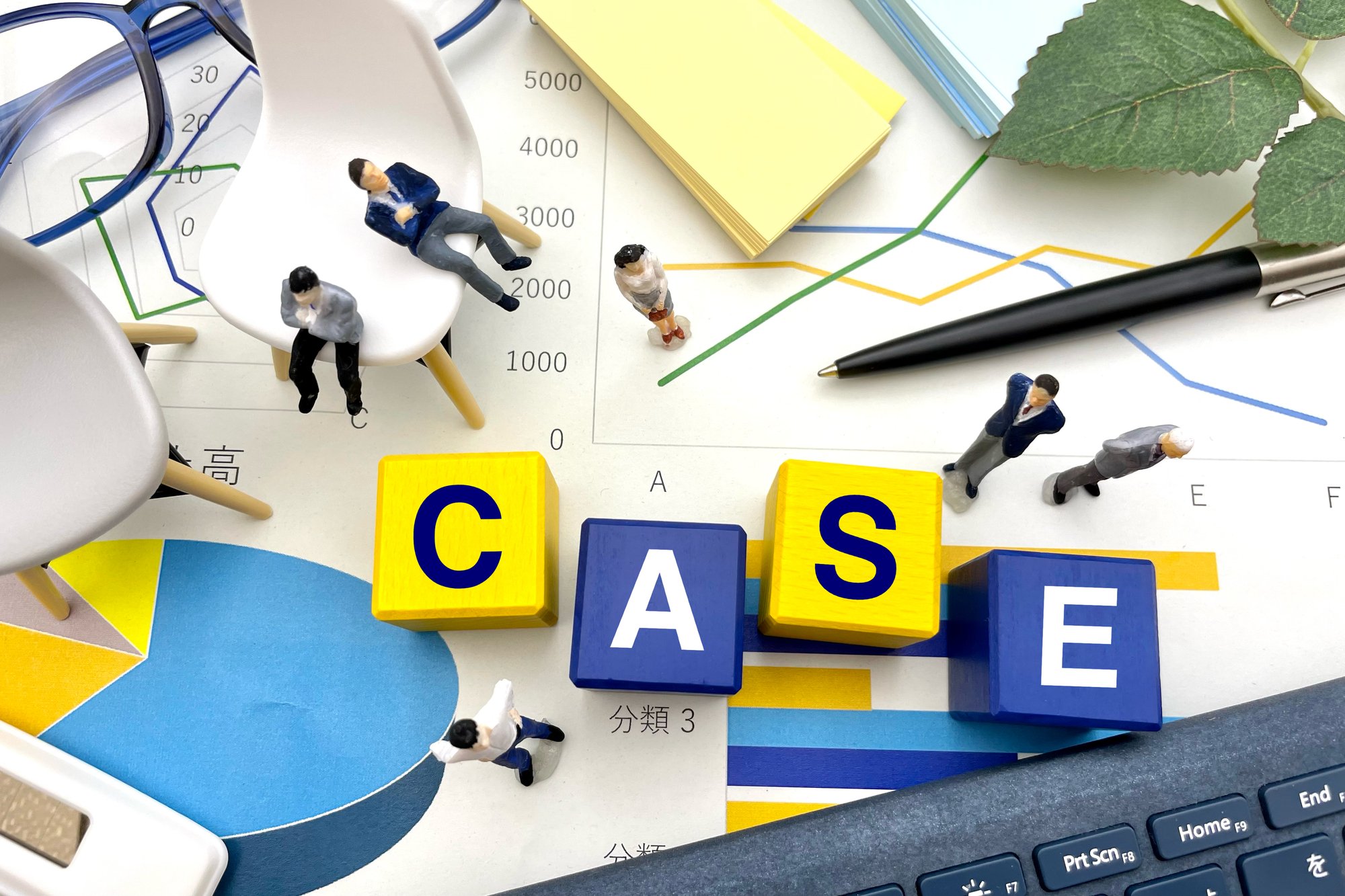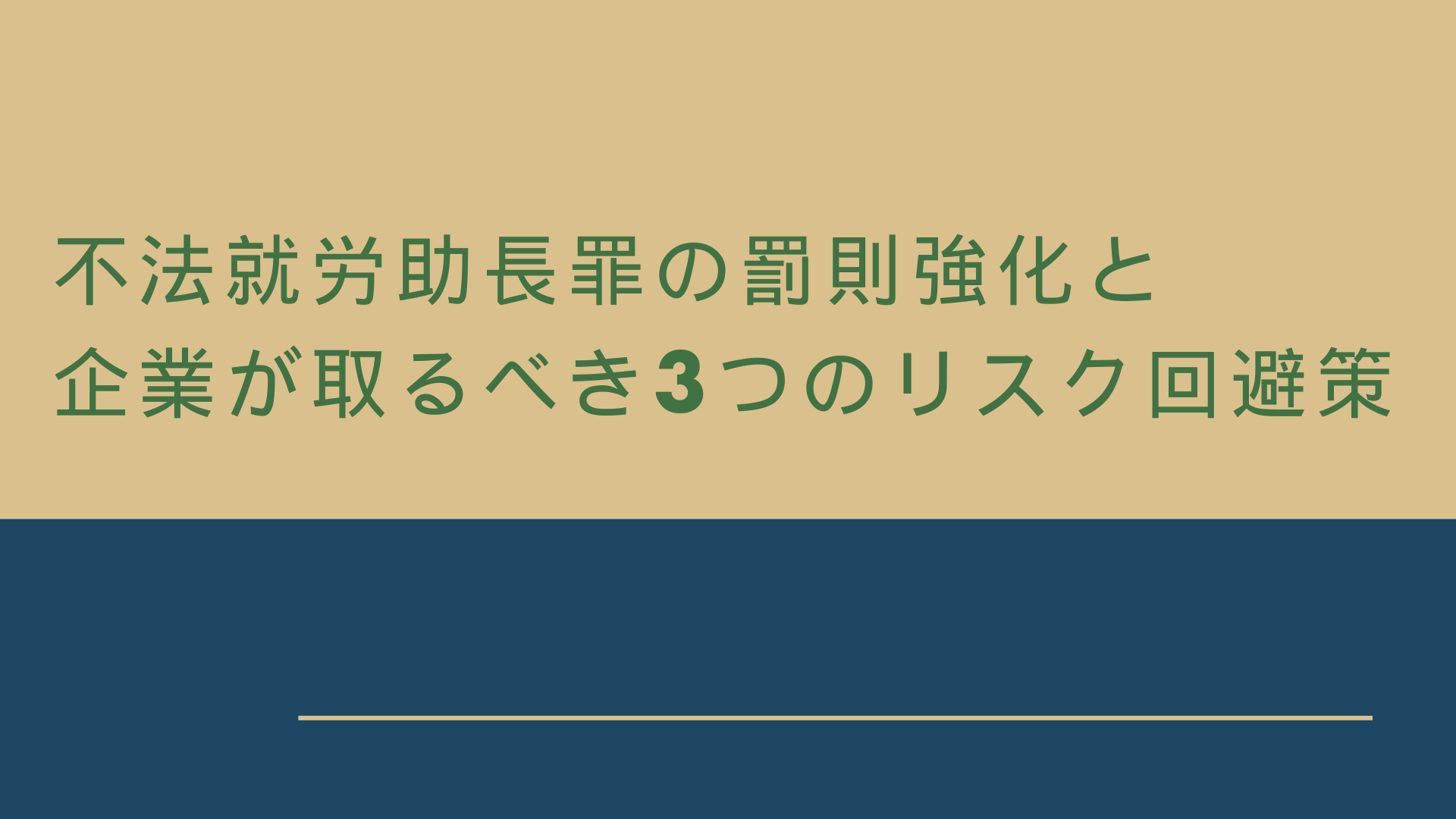
外国人材の採用を検討されている人事・採用ご担当者様、経営者様、
「外国人採用に興味はあるけれど、法律や手続きが複雑そうで、一歩踏み出せない…」
「万が一、不法就労させてしまったら、会社にどんな責任が問われるのだろうか…」
このような不安を抱えていませんか?特に2025年6月からの罰則強化を前に、その懸念は一層深まっていることでしょう。
日本の労働市場において、外国人材は今や必要不可欠な存在です。しかし、制度への理解不足や確認の怠りから、意図せず不法就労をさせてしまい、事業主が重い処罰を受けるケースが後を絶ちません。企業に求められる責任は、これまで以上に大きくなっています。
この記事では、法就労助長罪の基本から、企業が「知らなかった」では済まされない具体的なケース、そして法的なリスクを回避するための実践的な対策まで、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、不法就労助長罪のリスクを正しく理解し、安心して外国人材採用を進めるための具体的な道筋が見えてくるはずです。最新の法改正情報と豊富な現場経験に基づき、貴社が外国人材を適法かつ安心して雇用するための「確かな知識」と「具体的なノウハウ」を提供します。ぜひ最後までお読みいただき、企業の外国人材採用に役立ててください。
目次
不法就労助長罪とは?2025年罰則強化の背景と企業が知るべき基本

外国人材の採用を検討する上で、まず理解しておくべきは「不法就労助長罪」という法律です。これは企業にとって非常に重い責任を伴うため、その基本をしっかりと押さえておきましょう。
■不法就労助長罪の定義と現行の罰則
不法就労助長罪は、入管法(出入国管理及び難民認定法)第73条の2に定められた法律です。これは、就労資格を持たない外国人を雇用したり、不法就労をあっせんしたりする行為を罰するものです。
この罪に問われた場合、以下の厳しい罰則が科せられます。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方
この罰則は、企業や事業主だけでなく、不法就労に関与した採用担当者や経営者個人も処罰の対象となり得ます。また、直接雇用だけでなく、業務委託や人材派遣の形で不法就労させてしまった場合も、同様に罪に問われる可能性がありますので、注意が必要です。
■【2025年6月~】法改正による罰則強化の具体的な内容
現在、法務省が提出した改正案により、不法就労助長罪の罰則は2025年6月からの施行が予定されており、さらに厳しくなる見込みです。
- 改正後の罰則:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
罰則が大幅に強化される背景には、不法残留者や不法就労者の増加が社会問題となっている現状があります。出入国在留管理庁の発表(令和6年1月1日現在)によると、不法残留者数は約7万9千人にのぼり、この問題に対する国の姿勢がより厳格化していることが分かります。
■「知らなかった」「過失」では済まされない企業の責任
この罪が特に企業にとって恐ろしいのは、故意でなくても処罰の対象となる点です。
「外国人本人が嘘をついた」「在留カードの確認をうっかり忘れていた」といった、企業側の確認不足(過失)があったと判断された場合でも、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
これは、企業に「外国人を雇用する際には、その外国人が適法に就労できる身分であるかを確認する義務がある」と法律が定めているからです。
企業が「意図せず」陥りやすい!不法就労の3つの具体例
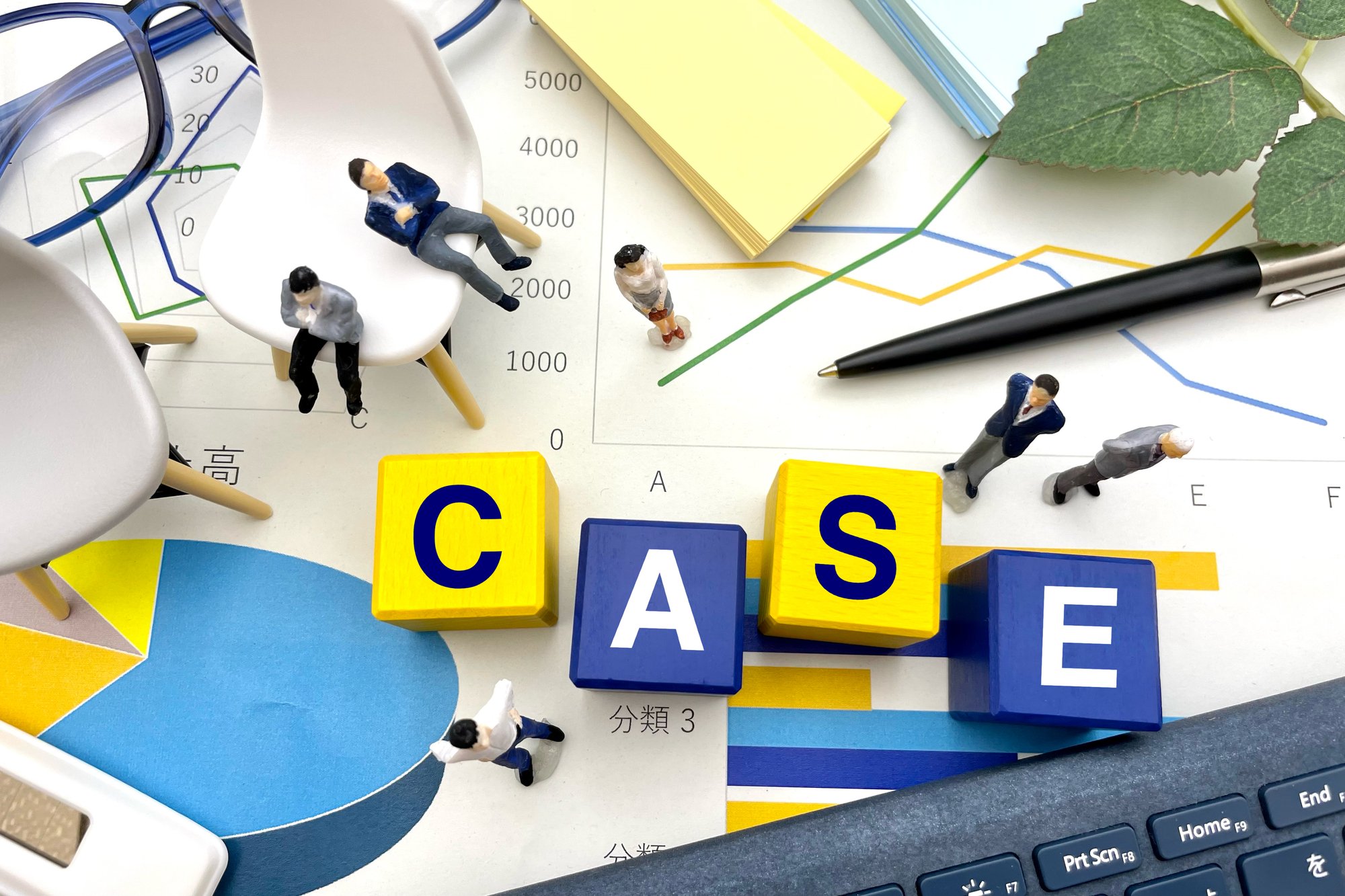
不法就労は、単に「不法滞在者を雇用する」ことだけではありません。企業が意図せず陥りやすい、以下の3つのケースを理解しておくことが重要です。
■不法滞在者を雇用してしまったケース
これは最も分かりやすいケースです。在留期間が切れたオーバーステイの外国人や、密入国者、退去強制が決まっている被退去強制者を雇用した場合がこれに該当します。採用時に在留カードの有効期限をしっかりと確認することが不可欠です。
しかし、さらに注意が必要なのは、採用後に不法滞在状態になるケースです。
採用時は適法でも、その後、本人が在留期間の更新手続きを忘れて不法滞在状態になってしまうこともあります。雇用側が定期的な確認を怠ると、知らないうちに不法就労させてしまうリスクがありますので、定期的な在留資格の確認は非常に重要です。
就労ビザの更新完全ガイド!許可申請・必要書類・手続きの流れを徹底解説
■就労が認められない在留資格者を雇用したケース
観光目的の「短期滞在」ビザや、「留学」「家族滞在」ビザなど、原則として就労が認められていない在留資格を持つ外国人を雇用した場合も、不法就労となります。
これらの在留資格で働くには、「資格外活動許可」が必要です。雇用する際は、在留カードの裏面に「資格外活動許可」の記載があるか、そして許可されている活動範囲や時間(例:留学生は週28時間以内)を必ず確認しなければなりません。この確認を怠ると、企業も責任を問われることになります。
■在留資格で許可された活動範囲外の業務をさせたケース
就労が可能な在留資格であっても、許可された業務内容や業種以外で働かせると、不法就労とみなされます。
例えば、外国人料理人として在留資格「技能」を取得した外国人に、工場での軽作業やコンビニのレジ業務をさせた場合などがこれに該当します。その外国人が持つ在留資格は、特定の専門業務に限定されているため、それ以外の業務は許可されていない活動となるためです。
特定技能ビザで外国人材を雇用する場合も同様です。特定産業分野以外の業務に従事させることはできません。人事異動や業務の切り出しを行う際は、在留資格の活動範囲を正確に把握しておく必要があります。この点については、ご不安に思われる企業様も少なくないでしょう。
不法就労助長罪を回避するための3つの実践対策

「過失」による罪を回避するためには、採用プロセスと雇用後の管理において、以下の3つの対策を徹底することが不可欠です。
■対策1:在留カード・パスポートの徹底確認と偽造対策
外国人材を雇用する際は、必ず在留カードとパスポートの原本を確認します。これは基本中の基本であり、非常に重要なステップです。
特に在留カードは、偽造されるリスクがあるため、以下の点に細心の注意を払ってください。
- 有効期限、在留資格、就労制限の有無を必ず確認しましょう。
- 偽造防止技術(ホログラム、ICチップ、角度によって変わる文字など)を実際に目で見て確認してください。
- 出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会サービス」を利用し、カードが有効であるかを確認することも必須です。このサービスは出入国在留管理庁のウェブサイトで提供されており、無料で利用できますので、積極的に活用しましょう。
在留カード等番号失効情報照会サービス
■対策2:より確実な「就労資格証明書」の取得
在留カードの確認だけでなく、より確実にリスクを回避したい場合は「就労資格証明書」の取得が非常に有効です。
就労資格証明書とは、外国人本人の申請に基づき、出入国在留管理庁がその外国人が日本で就労できることを証明する書類です。企業がこの証明書の提示を求めることで、雇用側は「確認義務を怠っていない」と強く主張でき、過失による不法就労助長罪のリスクを大幅に低減できます。
■対策3:専門知識を持つパートナーの活用
不法就労助長罪のリスクを根本から排除し、安心して外国人材を雇用するには、専門知識を持つパートナーの存在が不可欠です。
企業の代わりに以下のサポートを提供し、法的なリスクから事業を守ります。
- 厳格な身分確認: 在留資格や就労資格の確認を徹底して行い、偽造や期限切れなどのリスクを未然に防ぎます。
- 適切な人材のマッチング: 企業の業務内容と、外国人材の在留資格で許可された活動範囲を照らし合わせ、法律を遵守しつつ、最大限に能力を発揮できる人材を厳選して紹介します。
- 雇用後のサポート: 在留期間の更新手続きの案内や、雇用中の相談にも対応し、継続的なコンプライアンス維持を支援します。
外国人材の採用は、単に法律を守るだけでなく、彼らが安心して働ける環境を整えることが成功の鍵となります。専門家のサポートを活用することで、企業は本業に集中しながら、外国人材の力を最大限に活かすことができるでしょう。
まとめ:厳罰化に備えて今すぐ行動を!

不法就労助長罪は、外国人材採用を検討するすべての企業にとって、絶対に無視できない経営リスクです。特に罰則強化は、この問題への意識をさらに高める必要があります。
「知らなかった」では済まされない時代において、重要なのは以下の2点です。
- 正確な知識の習得: 法律や制度を正しく理解し、自社で遵守するための体制を構築する。
- 信頼できるパートナーの活用: 専門的な手続きや管理を、実績豊富なサービスに任せることで、本業に集中できる環境を整える。
外国人材の採用を成功させるためには、法的なリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。STAYWORKERは、そのための確かな知識とサポートを提供いたします。
執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平
監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志
株式会社USEN WORKINGの外国人採用コンサルタント。人材紹介・派遣の法人営業として多くの企業の採用課題に、そして飲食店経営者として現場のリアルに、長年向き合ってきた経験を持つ。採用のプロと経営者、双方の視点から生まれる具体的かつ実践的な提案を信条とし、2022年の入社以来、介護・外食分野を中心に数多くの企業の外国人採用を成功に導く。