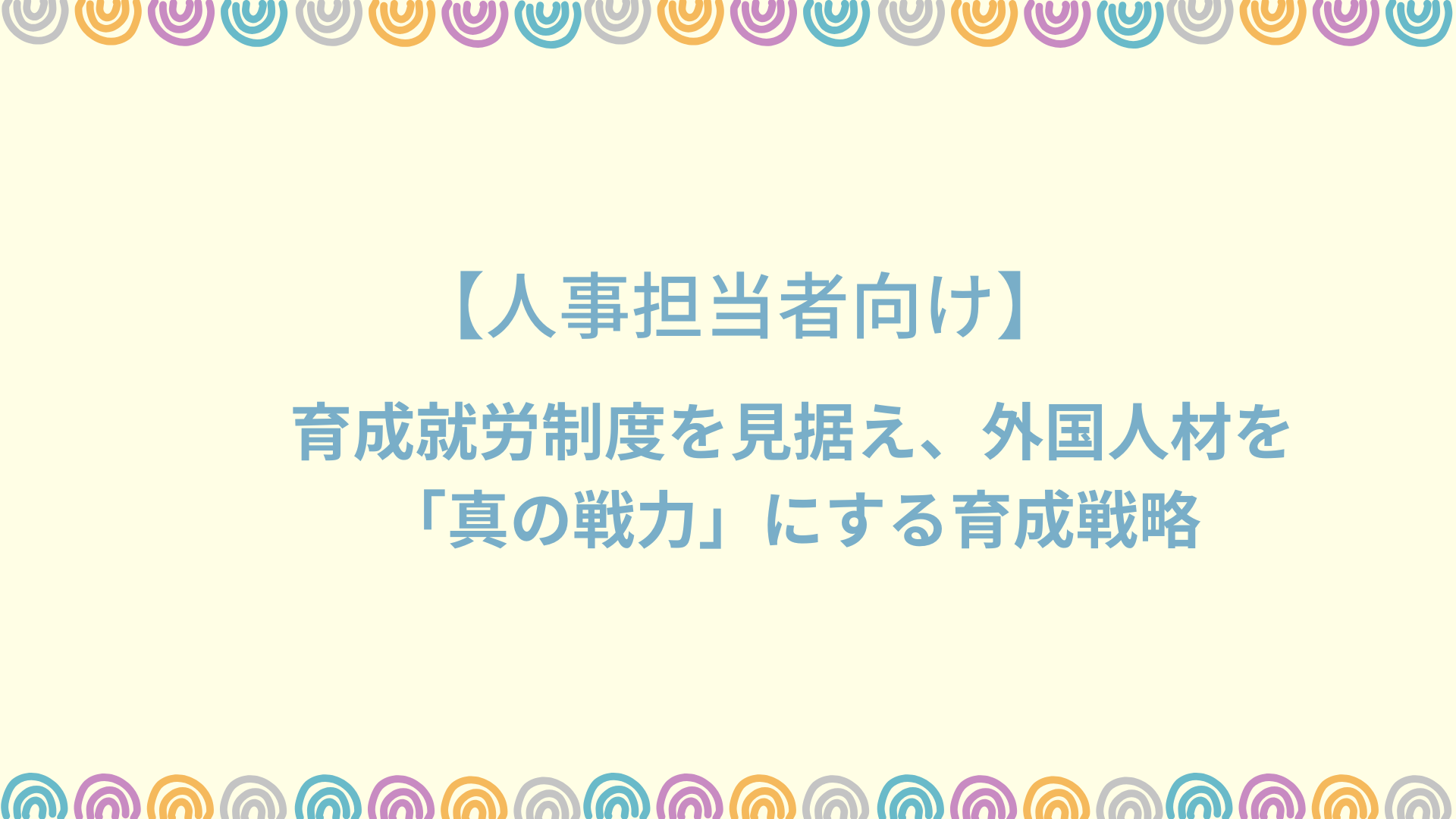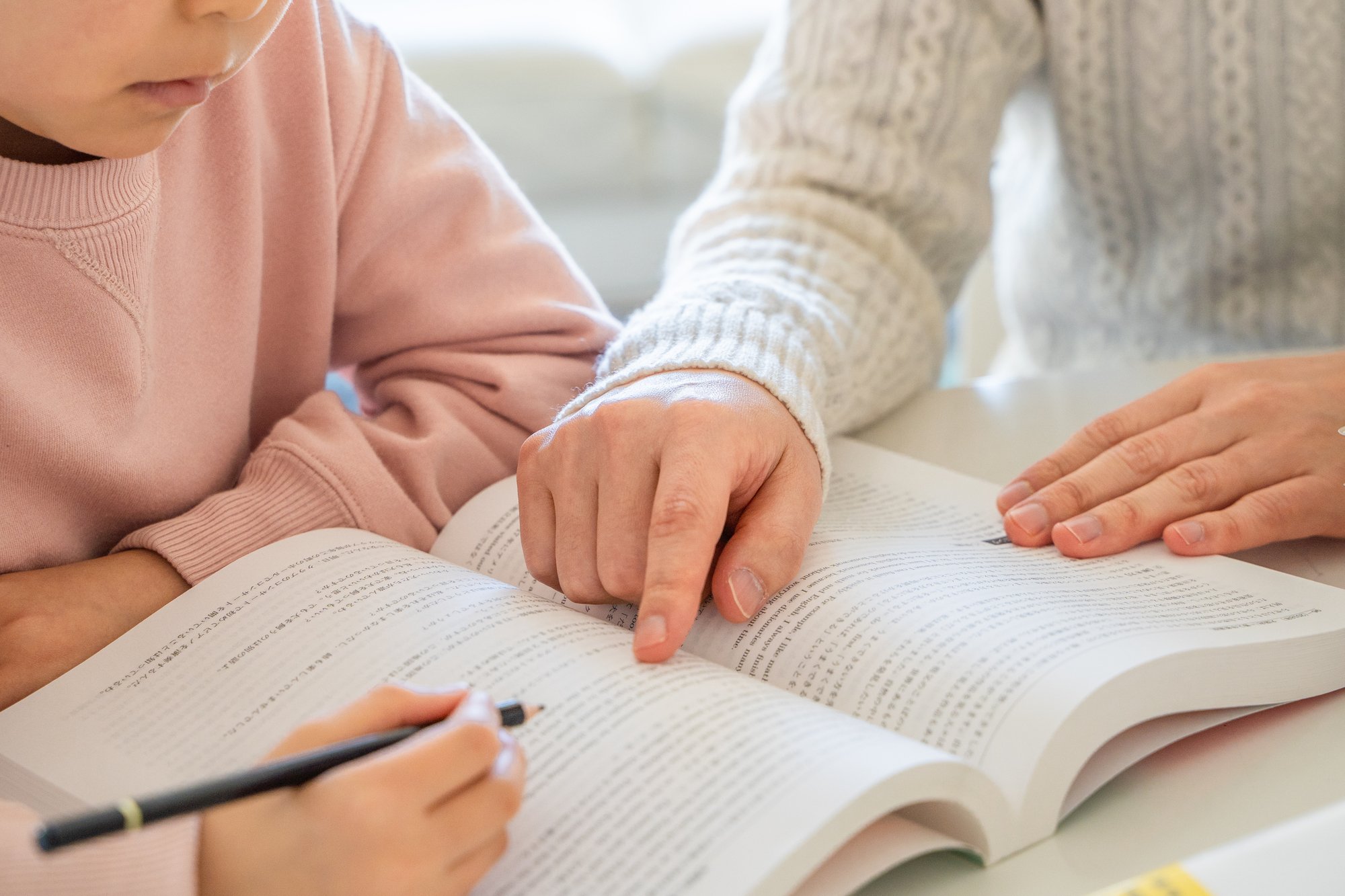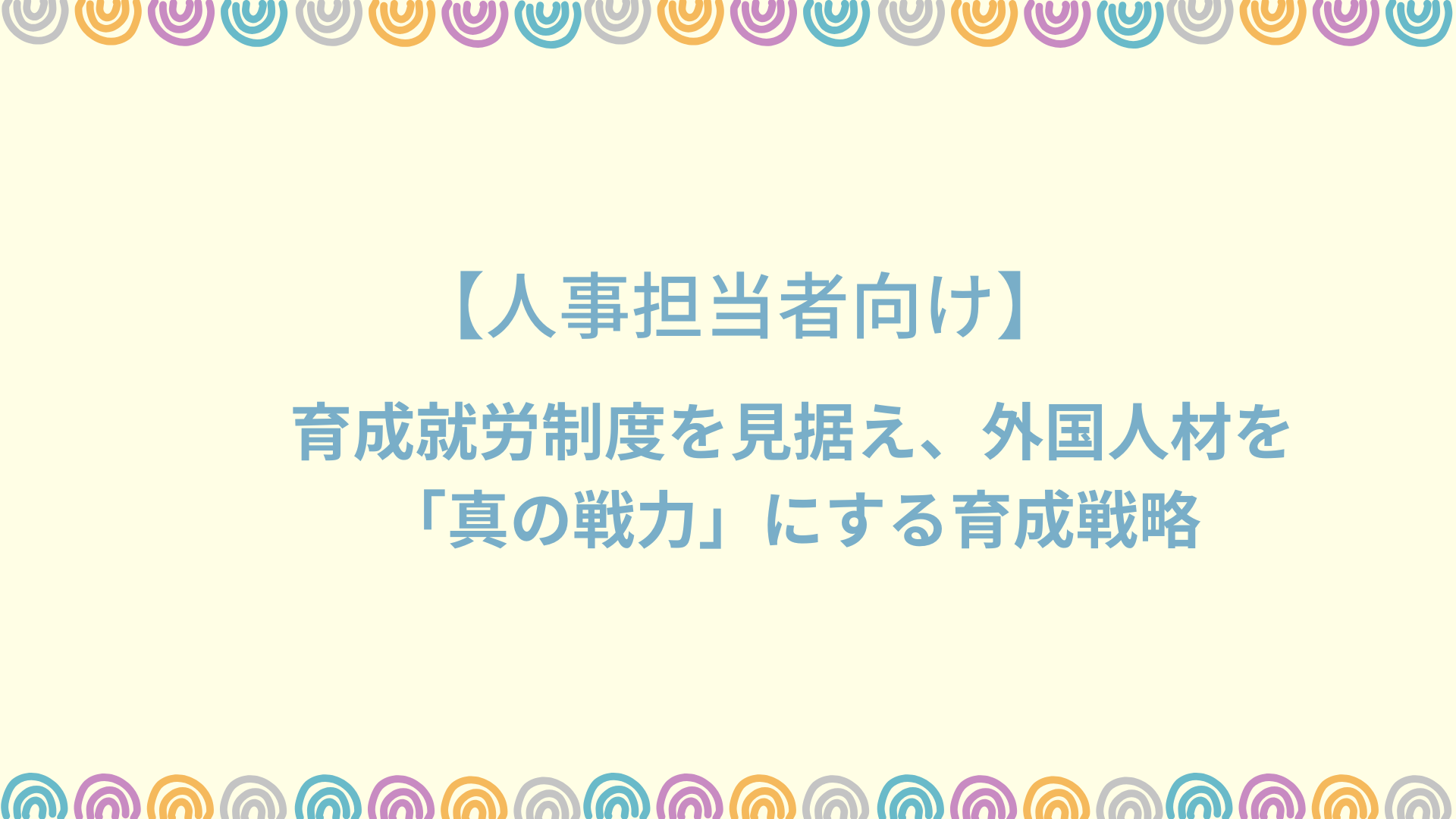
「特定技能の日本語試験、N4合格なら大丈夫」
そう思って採用を進めていませんか?
2027年施行の「育成就労制度」を目前に控え、日本語能力の要件は「採用時のチェックポイント」から「3年間の育成戦略の柱」へと本質的に変化しています。
本記事では、特定技能の日本語試験の基本から、競合が語らない「N4の壁」の乗り越え方、そして育成就労制度を見据えた未来の採用戦略まで、実践的なノウハウを徹底解説します。この記事を読めば、企業の外国人材採用が単なる人手不足解消ではなく、企業の成長を加速させる「投資」へと変わる確信が得られるでしょう。
目次
特定技能「日本語試験」の意義再定義、単なる合格基準を超えて

特定技能制度は、人手不足に悩む日本の産業を支えるために創設されました。外国人材が業務に必要な最低限の日本語能力を持つことを確認するため、日本語試験が要件として設けられています。しかし、この日本語試験の合格は、あくまでもスタートラインに過ぎません。
2027年4月に施行予定の「育成就労制度」を目前に控え、日本語能力の捉え方は、すでに根本的に変化し始めています。これからは、採用時のチェックだけでなく、入社後の「3年間を通じた育成戦略の柱」として、日本語教育を捉える視点が不可欠です。本記事では、この未来を見据えた採用戦略と、外国人材を真の戦力として定着させるための具体的な方法を解説します。
特定技能の日本語能力要件の「今」を知る
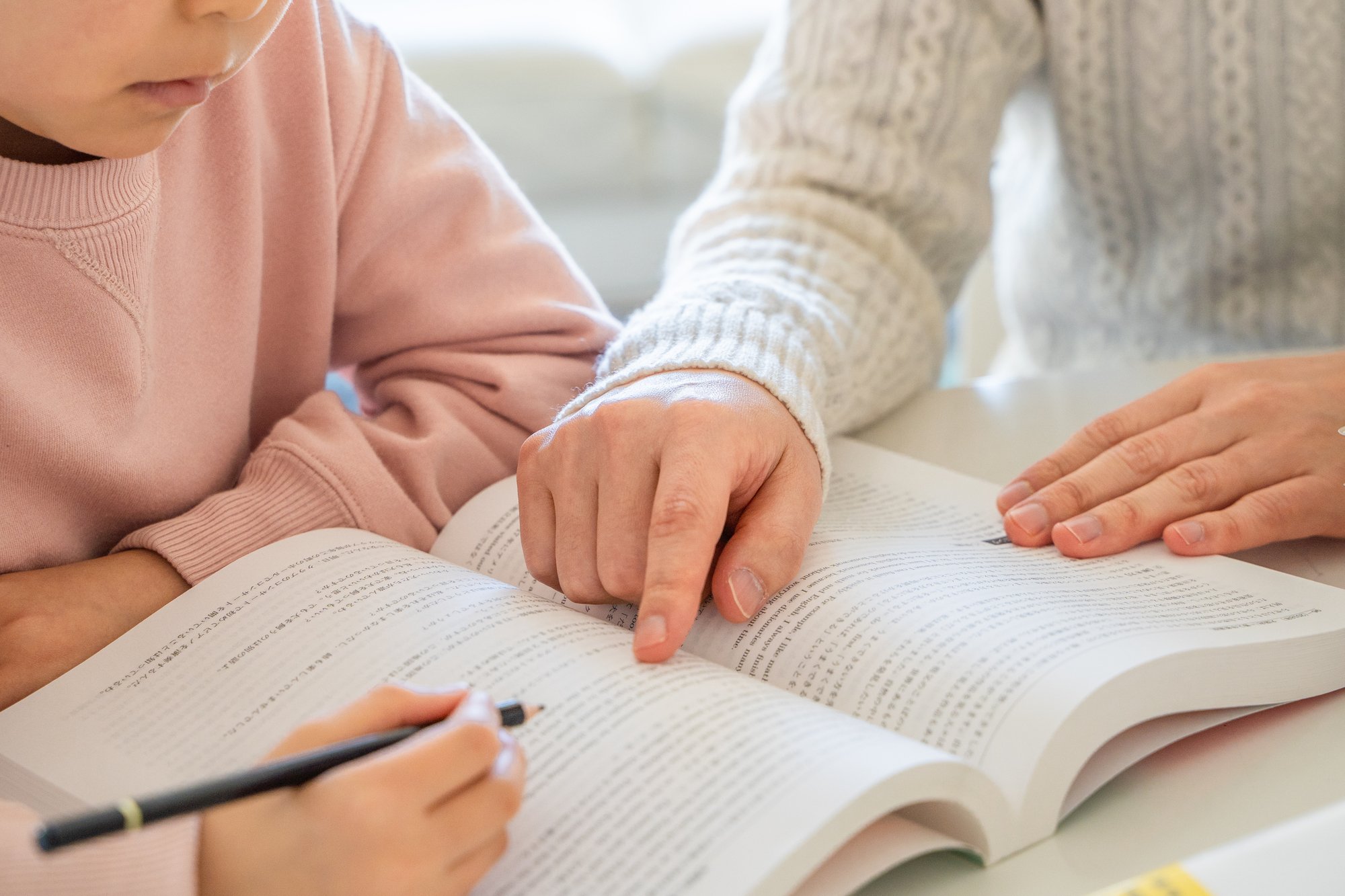
■特定技能1号の日本語能力要件:JLPT N4またはJFT-Basic A2
特定技能1号の在留資格を取得するためには、原則として日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上の日本語能力が求められます。これは、外国人材が日本での基本的な日常生活や業務において、円滑なコミュニケーションを図ることを目的としています。
JLPT N4は「基本的な日本語を理解できる」、JFT-Basic A2は「限定的ながらも基本的な会話ができる」レベルとされています。ただし、これらの試験に合格していても、必ずしもすべての外国人材が日本語試験を受ける必要はありません。例えば、技能実習2号を良好に修了した外国人材は、特定技能1号の日本語試験が免除されます。 これは、すでに日本での実務経験があり、一定の日本語能力と技能が身についていると判断されるためです
特定技能の分野別解説!最新情報と仕事内容を徹底ガイド
特定技能2号の取得条件とは?移行方法や試験内容を徹底解説!
■JLPTとJFT-Basic:企業が「戦略的に」選ぶポイント
特定技能の日本語能力を証明する試験には、主に「日本語能力試験(JLPT)」と「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の2種類があります。どちらの試験を選ぶかは、企業の採用計画によって戦略的に判断すべきです。
JLPTは世界中で実施され、日本語学習者の間で最も広く認知されている試験です。年に2回(7月と12月)実施され、結果通知まで時間がかかる傾向があります。一方、JFT-Basicはより頻繁に実施され、結果も比較的早く出るため、採用を急ぐ場合や、特定の国からの採用が多い場合に有効な選択肢となり得ます。
たとえるなら、JLPTが大学の一般入試だとすれば、JFT-Basicは高専の推薦入試のようなものです。それぞれに特性があるため、採用スケジュールや対象国籍、外国人材の学習状況に合わせて最適な試験を選ぶことが重要です。
育成就労制度が変える日本語要件の未来

■育成就労制度(I.S.S.)とは?特定技能への影響の全体像
2027年4月に施行が予定されている育成就労制度(I.S.S.)は、現行の技能実習制度に代わる新たな外国人材受け入れ制度です。その大きな目的は、「人材確保と育成」であり、特定技能への明確なキャリアパスを設定することにあります。
この制度導入により、日本語能力の要件は単なる「採用時のチェック」から「3年間の育成戦略の柱」へと根本的に変化します。2025年7月現在、企業様がI.S.S.の最新動向を把握しておくことは、将来的な人材確保における先行者利益の獲得、および予期せぬリスク回避のために極めて重要です。
■日本語要件の「義務化」が企業に求める新たな育成戦略
育成就労制度では、日本語能力の段階的な向上が義務付けられる見込みです。具体的には、入国時にN5相当の日本語能力、そして特定技能への移行時にはN4/N3レベルが目標とされています。これらの要件は、現行の特定技能制度と比較して、企業側の育成責任が大幅に増加することを意味します。
なお、育成就労制度に関する詳細な日本語教育義務の内容、施行スケジュール、関連する省令やガイドラインは、現時点(2025年7月)ではまだ確定していない部分も多く、今後の政府発表を注視し、最新情報を確認することが重要です。STAYWORKERでは、常に最新の情報をキャッチアップし、企業様へ的確なアドバイスを提供しています。
この義務化は、企業に以下のような具体的な影響を与えます。
- 日本語教育体制の構築:N5レベルから段階的に日本語教育を行うための計画と実行が必須となります。
- 教育コストの計画:教育にかかる費用や時間も、採用計画に組み込む必要があります。
- 転職・転籍可能性への対応:育成就労制度では、条件付きで転職・転籍が可能となるため、優秀な人材に選ばれるための日本語支援が定着に直結します。
日本語教育が採用後の「義務」となることで、企業側の「育成責任」はより明確になります。これからは、外国人材が「選べる」時代へと変化していくでしょう。企業が選ばれるためには、積極的かつ効果的な日本語支援が不可欠です。
■技能試験合格と日本語能力:見落とされがちな重要な関係性
特定技能の在留資格には、日本語能力試験だけでなく、各分野の「技能試験」の合格も必須です。しかし、この技能試験においても、日本語能力は合否を左右する不可欠な要素であるという点は見落とされがちです。
試験問題の読解、指示の理解、質疑応答など、日本語能力が不足していると、本来の技能があっても試験で実力を発揮できない可能性があります。さらに、入社後のOJT(On-the-Job Training)や実務研修においても、専門用語の理解や安全管理に関する指示の正確な把握は、業務効率や職場の安全、ひいては外国人材の定着率に大きく影響します。
企業側は、単に日本語試験や技能試験の合格を目標とするだけでなく、入社後のOJTを見据えた「現場特化型」の日本語教育の重要性を認識し、取り組むべきでしょう。
N4合格だけでは不十分?現場の「N4の壁」を乗り越える実践戦略

■「N4レベル」の現実:現場で起こるコミュニケーションギャップ
特定技能の日本語能力要件であるJLPT N4またはJFT-Basic A2レベルは、「日常生活で使われる基本的な日本語をある程度理解できるレベル」と定義されています。しかし、この制度上の定義と、現場で実際に求められる日本語能力の間には、大きなギャップが存在します。つまり、試験に必要な日本語能力の基準と、職場で本当に必要な日本語能力には大きな違いがあるということです。
安全管理のリスク:専門用語や複雑な手順を含む安全指示の聞き間違い、理解不足は、重大な事故発生リスクに直結します。例えば、介護現場での緊急対応や、工場での機械操作など、一瞬の判断が命取りになる場面は少なくありません。
- 業務効率の低下:報告・連絡・相談(ホウレンソウ)の遅延や、意図しないコミュニケーションミスは、作業の停滞を招き、全体の業務効率を低下させます。飲食店のオーダーミスもその一例です。
- 心理的孤立と早期離職:日本人従業員との円滑なコミュニケーションが取れないことは、外国人材が職場で孤立し、モチベーションの低下や早期退職(定着率の悪化)につながる最も大きな原因の一つです。
この「N4の壁」を乗り越えることこそが、特定技能外国人材を真の戦力として長期的に定着させるための、最大の課題と言えるでしょう。
■企業が取り組むべき日本語教育の強化と実践ノウハウ
外国人材を真の戦力として育成し、定着させるためには、日本語試験合格後の継続的な日本語教育への投資が不可欠です。
そのため、特に重要なのは、現場特化型教育です。これは、一般的な単語の暗記に留まらず、企業の業務で実際に使用される特定の動詞やフレーズ、手順説明に焦点を当てたカリキュラムを設計することを意味します。例えば、介護現場であれば身体介助に関する専門用語、飲食店であれば接客用語や調理手順の指示など、実践的な日本語能力を養うことが重要です。
また、地理的な制約や勤務時間の都合がある場合でも、オンライン日本語教育サービスやEラーニングを活用することで、効率的かつ継続的に学習できる環境を提供できます。入社前研修、OJTと連動した学習、定期的なレベルチェックなどを組み合わせた日本語教育プログラムを設計し、継続的に提供することで、外国人材は着実に日本語能力を向上させ、定着を促すことができるでしょう。
■定着率を劇的に変える「日本人社員側の意識改革」3つのポイント
外国人材の定着率を向上させるためには、外国人側の日本語教育だけでは不十分です。日本人従業員側の意識改革もまた、不可欠な要素となります。コミュニケーション問題の背景には、「言語の壁」だけでなく、「文化や価値観の違い」や「日本人従業員側の理解不足」も大きく影響しています。
企業が実施すべき具体的な対策を3つのポイントでご紹介します。
- 異文化理解研修・ダイバーシティ研修の実施:
日本人従業員が異文化への理解を深めることで、外国人材との円滑なコミュニケーションを促し、相互理解を深めることができます。
- 「やさしい日本語」の社内マニュアル化:
誰でも理解しやすい言葉遣いを社内で徹底することは、情報伝達の精度とスピードを向上させ、業務効率化に貢献します。専門用語を避け、簡単な単語や短文で話すことを意識しましょう。
- 積極的な声かけとサポート体制の構築:
外国人材が孤立しないよう、日本人社員が積極的に声かけを行い、心理的安全性の高い職場環境を築くことが重要です。質問しやすい雰囲気作りや、困りごとを相談できる体制を整えましょう。
これらの取り組みを通じて、外国人材が安心して働ける環境を整えることが、定着率を劇的に向上させる鍵となります。
まとめと次のアクション:未来を見据えた採用戦略を今、始める

2025年、あなたの採用戦略は「未来」に対応できていますか?
この記事を通じて、企業の人事担当者様は、特定技能の日本語試験要件(N4/A2)が現場での業務遂行には不十分であること、そして採用後の育成戦略こそが外国人材の定着・戦力化の鍵であることを深くご理解いただけたのではないでしょうか。
特に2025年7月現在、2027年導入予定の育成就労制度(I.S.S.)を見据え、日本語教育を単なる「要件」ではなく「義務」と捉え、長期的な視点で採用戦略を練ることの重要性を深く認識されたことと思います。企業の採用戦略は、刻々と変化する制度と現場のニーズに、もう対応できていますか?
制度改正を追い風とし、採用の門戸を広げて多様な専門性を持つ人材を受け入れることで、組織の柔軟性を高める企業が目立ち始めています。変動する時代に対応できる組織づくりこそが、今後の人材戦略を成功させる鍵となります。
執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平
監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志
株式会社USEN WORKINGの外国人採用コンサルタント。人材紹介・派遣の法人営業として多くの企業の採用課題に、そして飲食店経営者として現場のリアルに、長年向き合ってきた経験を持つ。採用のプロと経営者、双方の視点から生まれる具体的かつ実践的な提案を信条とし、2022年の入社以来、介護・外食分野を中心に数多くの企業の外国人採用を成功に導く。