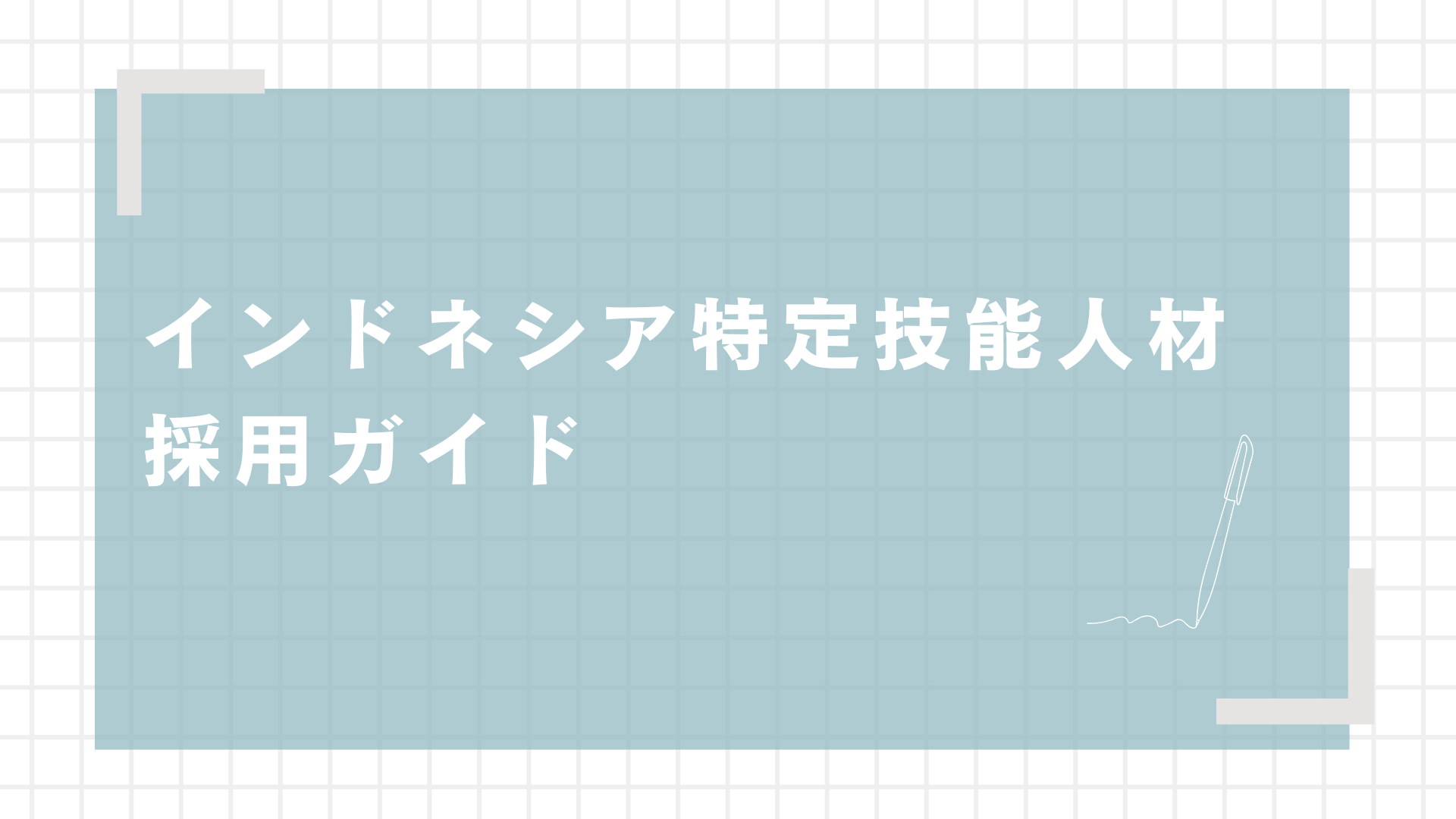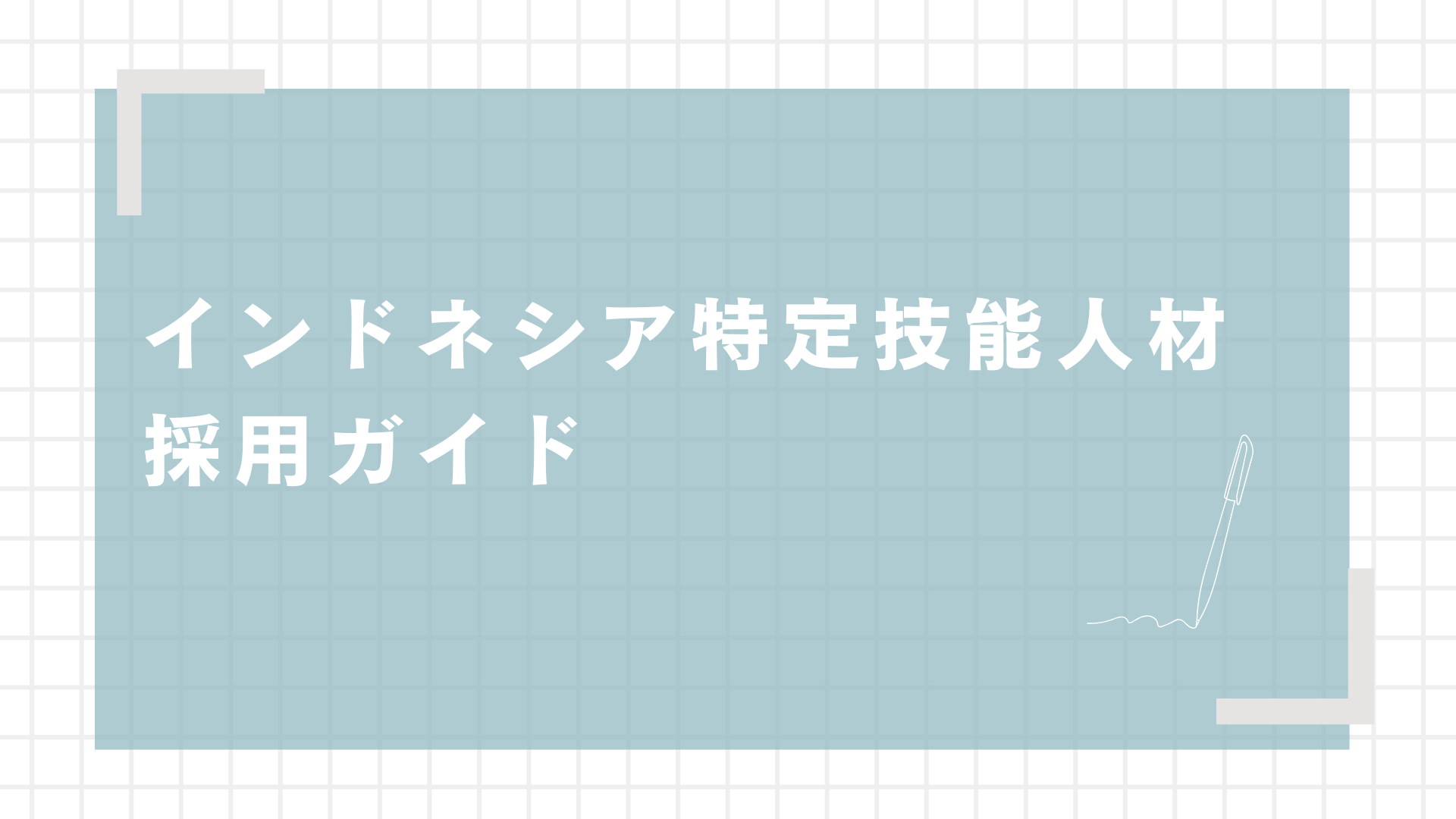
国内人材の確保が困難になり、外国人採用を検討する中で、「インドネシア特定技能」にたどり着いたものの、複雑な手続き、不透明な費用、そして何より信頼できる情報源の少なさに頭を抱えていませんか?本記事では、最新の日本・インドネシア間協力覚書(MOC)の内容を踏まえ、インドネシア人特定技能人材の採用に関する最も網羅的で、透明性が高く、かつ最新の公的情報を徹底解説します。IPKOLやSISKOTKLNといったインドネシア政府固有のシステムから、P3MI(送り出し機関)を介さないコスト削減の可能性、そして採用後の定着支援まで、企業が抱える疑問と不安を解消し、自信を持って採用を進めるための具体的なステップと知見を提供します。
この記事を読めば、企業が自力で手続きを進める際の確かな羅針盤となり、悪質なブローカーに惑わされることなく、コンプライアンスを遵守した安心・安全な人材確保が実現するでしょう。
目次
なぜ今、インドネシア人特定技能人材なのか?

■深刻化する人手不足と外国人材活用の必要性
日本社会では、少子高齢化に伴う労働力人口の減少が深刻化しています。特に地方の製造業や介護業界では、慢性的な人手不足が事業継続の大きな課題となっており、この状況は今後も続くと見られています。例えば、
厚生労働省の統計によると、2024年時点での介護分野の有効求人倍率は約4倍に達しており、人材確保の喫緊性が浮き彫りになっています。外国人材の活用は、もはや一時的な対策ではなく、企業の持続的な成長に不可欠な経営戦略と言えるでしょう。
■インドネシアが注目される3つの理由(政府の積極支援、日本語学習意欲、MOC)
インドネシアからの特定技能人材採用には、多くのメリットがあります。主に以下の3つの理由から、今、インドネシアが注目されています。
- インドネシア政府の積極的な送り出し支援体制:インドネシア政府は、自国民の海外就労を国策として積極的に推進しています。これにより、政府機関が関与する制度が整備されており、比較的安心して人材を受け入れられる環境が整っています。
- 高い日本語学習意欲と適応力:インドネシアは親日的な国民性が特徴で、日本語学習への意欲が高い人材が多く存在します。また、異文化への適応力も高く、日本での生活や職場環境にもスムーズに馴染む傾向が見られます。
- 最新のMOC(協力覚書)締結:2024年6月25日に日本とインドネシア間で更新された協力覚書(MOC)は、両国間の特定技能人材の交流をさらに促進する強力な基盤となります。これにより、より円滑な人材送出し・受入れが期待されます。
■他国と比較!インドネシア人材の強みと特徴
ベトナムやフィリピンなど、他の主要な送り出し国と比較しても、インドネシア人材には独自の強みがあります。
- 勤勉で温厚な性格:イスラム教徒が多い背景から、規律を重んじ、真面目で勤勉な国民性が特徴です。また、温厚な性格のため、職場での人間関係も良好に築きやすいと言われています。
- 日本語習得のポテンシャル:母国語がインドネシア語であり、日本語との文法構造に共通点があるため、日本語学習が進みやすいという意見もあります。
- 高い定着率の傾向:過去のデータでは、インドネシア人特定技能人材の定着率は比較的高く、長期的な雇用に繋がりやすいという報告もあります。
インドネシア特定技能制度の全体像

■特定技能制度とは?1号と2号の違い
特定技能制度は、日本の中小企業における人手不足を解消するため、2019年4月に創設された在留資格です。専門的な技能と知識を持つ外国人材を、特定の産業分野で受け入れることを目的としています。
特定技能には1号と2号があり、主な違いは以下の通りです。
- 特定技能1号:特定の産業分野で就労する外国人向けの在留資格です。在留期間は最長5年で、家族の帯同は認められていません。
- 特定技能2号:特定技能1号で培った技能をさらに熟練させた外国人向けの在留資格です。在留期間の更新が可能で、家族の帯同も認められています。
特定技能とは?
■インドネシアにおける特定技能制度の枠組みと特徴
インドネシア政府は、特定技能制度を通じて日本へ人材を送り出すことに積極的です。インドネシア側では、政府機関が送り出しプロセスに関与し、適切な人材選定と管理が行われる枠組みが構築されています。
特定技能制度を、日本とインドネシアが協力して築き上げた「人材の架け橋」とたとえるなら、MOC(協力覚書)はその橋の設計図であり、両国が安全かつスムーズに人材が行き来するためのルールブックです。このMOCに基づき、両国政府が協力して制度を運用することで、透明性と信頼性の高い人材交流が実現しています。
■受け入れ可能な職種・分野と人材要件
特定技能1号で受け入れ可能な職種・分野は、2025年7月現在、以下の16分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
外国人材が特定技能の在留資格を得るためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 技能水準:各分野で定められた技能試験に合格していること。
- 日本語能力水準:日本語能力試験(JLPT)N4相当以上の日本語能力を有していること。ただし、介護分野では、高齢の入居者様との円滑なコミュニケーションが求められるため、より高い日本語能力や、介護に特化した専門用語の理解が重要視される傾向にあります。
- 年齢:18歳以上であること。
- 健康状態:健康診断の結果が良好であること。
- 欠格事由:過去に不法滞在や犯罪歴がないこと。
【最重要】インドネシア政府公認システム「IPKOL」「SISKOTKLN」を徹底解説

インドネシア人特定技能人材を採用する上で、最も重要かつ複雑に感じられるのが、インドネシア政府が運用する「IPKOL」と「SISKOTKLN」という2つのシステムです。これらのシステムへの登録と適切な利用は、コンプライアンス遵守のために不可欠です。
■ IPKOLとは?役割と登録の重要性
IPKOL(Sistem Informasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri)は、「インドネシア海外移住労働者配置情報システム」と訳され、インドネシア人労働者を海外に送り出す際の情報を一元管理するシステムです。日本企業がインドネシア人特定技能人材を雇用する場合、このIPKOLへの企業登録が義務付けられています。
IPKOLは、日本企業にとって、まるで「
海外人材採用の公式パスポート(または登録証)」のようなものです。このパスポートがなければ、インドネシア政府から人材を受け入れるための正式な手続きを進めることができません。登録の法的根拠は、日本とインドネシア間のMOCに明記されています。
IPKOLに関する最新の政府ガイドラインや変更点は、インドネシア労働省(Kementerian Ketenagakerjaan)のウェブサイト等で公表されております。
■SISKOTKLNとは?役割と登録の重要性
SISKOTKLN(Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri)は、「海外労働者コンピュータ化システム」と訳され、インドネシア人労働者個人の海外就労履歴や情報を管理する公式データベースです。
SISKOTKLNは、IPKOLと連携し、インドネシア人労働者の出国から帰国までの一連の情報を記録します。例えるなら、「
インドネシア人労働者の海外就労履歴を管理する公式データベース」であり、労働者一人ひとりの情報が正確に登録されていることが重要です。企業側は、IPKOL登録を通じて、このSISKOTKLNに雇用する人材の情報が適切に反映されているかを確認する必要があります。
SISKOTKLNに関する最新の政府ガイドラインや変更点も、IPKOLと同様にインドネシア政府機関から公表されており、STAYWORKERが正確な情報に基づいてサポートを提供します。
■IPKOL/SISKOTKLNの具体的な登録・利用方法(日本企業向け)
日本企業がIPKOLに登録する際の基本的なステップは以下の通りです。
- アカウント作成:IPKOLのウェブサイトで企業アカウントを作成します。
- 企業情報の入力:会社名、所在地、連絡先などの基本情報を入力します。
- 必要書類のアップロード:企業登録証明書、事業許可証、雇用契約書(案)などの書類をスキャンしてアップロードします。
- 審査と承認:提出された情報と書類がインドネシア政府によって審査され、承認されると登録が完了します。
SISKOTKLNへの情報入力は、主にインドネシア人労働者本人や、P3MI(送り出し機関)が行いますが、企業側は雇用する人材の情報が正確に登録されているかを確認する責任があります。
これらの手続きは、慣れない企業様にとっては複雑に感じられるかもしれません。よくある疑問としては「どの書類が必要か」「入力方法が分からない」「審査に時間がかかる」といった声が聞かれます。
インドネシア人特定技能人材の採用手続きフロー(日本側・インドネシア側)

インドネシア人特定技能人材の採用は、日本側とインドネシア側の両方で並行して手続きを進める必要があります。全体像を把握し、計画的に進めることが成功の鍵となります。
■採用活動の開始から入国までの全体フロー
特定技能人材の採用は、まず企業の採用計画策定から始まります。その後、人材募集、選考、そして在留資格申請、入国、就労開始へと至ります。この一連のプロセスは、日本国内での手続きとインドネシア国内での手続きが密接に連携しています。
■日本国内での手続き(在留資格申請、雇用契約など)
日本国内で企業が行う主な手続きは以下の通りです。
- 雇用契約書の作成:労働条件や給与などを明記した雇用契約書を作成します。記載すべき内容は法務省令で定められており、細心の注意が必要です。
- 支援計画書の作成:特定技能外国人への支援内容を定めた計画書を作成します。自社で支援を行う場合は、適切な支援体制を整える必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請(COE):企業が外国人材を受け入れるための許可証であるCOEを、地方出入国在留管理局に申請します。必要書類は多岐にわたり、審査期間は数週間から数ヶ月かかる場合があります。
■インドネシア国内での手続き(P3MIの関与、出国手続きなど)
インドネシア国内での手続きは、P3MI(送り出し機関)を介するか、自社で直接進めるかによって異なります。
- P3MIを介する場合:P3MIが人材募集、選考、現地での日本語教育、健康診断、ビザ申請、IPKOL/SISKOTKLNへの登録・情報入力、渡航手続きなどを代行します。
- 自社で直接進める場合:企業自身でIPKOLへの企業登録を行い、雇用する人材のSISKOTKLNへの情報入力状況を確認します。健康診断やビザ申請、渡航手続きについても、企業が現地で調整を行うか、信頼できる現地のパートナーの協力が必要となります。
■【国内在留者向け】技能実習・留学生からの移行手続き
既に日本に在留している外国人材(技能実習修了者や留学生など)を特定技能に移行させることも可能です。このルートには、以下のようなメリットがあります。
- 日本語能力:日本での生活を通じて、既に一定の日本語能力を習得していることが多いです。
- 日本での生活慣れ:日本の文化や習慣、職場環境に慣れているため、入国後の適応期間が短縮されます。
移行に必要な要件としては、特定技能の技能試験・日本語試験への合格(または免除要件を満たすこと)、現在の在留資格の適正な履行などが挙げられます。手続きの流れとしては、在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に行う形となります。
採用コストを最適化!P3MI(送り出し機関)の役割と不要性

インドネシア人特定技能人材の採用において、最も気になる点の一つが費用ではないでしょうか。特に、P3MI(送り出し機関)の利用について、その役割と費用、そして利用の必要性を正しく理解することが、コスト最適化に繋がります。
「高額な費用がかかるのでは?」という不安を解消し、企業にとって最適な採用方法を見つけるお手伝いをします。
■P3MI(送り出し機関)とは?その役割と費用構造
P3MI(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)は、「インドネシア移住労働者配置会社」と訳され、インドネシア政府から認定を受けた、海外への人材送り出しを専門とする機関です。P3MIは、人材の募集・選考、日本語や技能の事前教育、健康診断、ビザ申請、渡航手配、そしてIPKOL/SISKOTKLNへの登録サポートなど、多岐にわたるサービスを提供します。
P3MIを利用した場合、通常、企業側は紹介料やサポート費用をP3MIに支払うことになります。その費用の内訳や相場は、P3MIによって異なりますが、数十万円から百万円を超えるケースも少なくありません。
例えるなら、P3MIを「
海外旅行の手配を全てお任せできる旅行代理店」とたとえるなら、自社採用は「
自分で航空券や宿泊先、観光ルートを全て手配する自由旅行」のようなものです。
■P3MIは必須ではない!コスト削減の可能性と自社採用の道
インドネシアからの特定技能人材採用において、
P3MIの利用は法的に必須ではありません。これは、多くの企業様が誤解されやすいポイントです。P3MIを介さずに、企業が直接人材を募集し、必要な手続きを自社で行う「
自社採用」も可能です。
自社採用を選択することで、P3MIに支払う高額な紹介料や手数料を削減できるため、大幅なコストメリットが見込めます。特に、慢性的な人手不足に悩む地方の製造業や介護施設にとって、採用コストの削減は非常に重要な課題です。
■P3MIを利用しない場合の注意点とリスクヘッジ
P3MIを介さない自社採用は、コスト削減の大きな魅力がある一方で、企業が直接行うべき手続きが増えるという側面もあります。
- 手続きの複雑さ:IPKOL/SISKOTKLNへの登録、現地での各種調整(健康診断、ビザ申請など)は、専門知識と時間が必要です。
- 情報収集の難しさ:最新の政府ガイドラインや現地の状況に関する情報を自力で収集し続ける必要があります。
- 悪質なブローカーへの対策:現地の不透明なブローカーに騙されるリスクも考慮しなければなりません。
登録支援機関の活用と選定のポイント

特定技能外国人を受け入れる企業には、外国人材への支援計画の作成と実施が義務付けられています。この支援を、自社に代わって行うのが「登録支援機関」です。
「自社でどこまで支援できるか不安」「初めての外国人採用なので専門家の力を借りたい」といった企業様にとって、登録支援機関は心強い存在です。
■登録支援機関の役割と支援内容
登録支援機関は、特定技能外国人が日本で安心して働き、生活できるよう、企業に代わって様々な支援を行う専門機関です。
具体的な支援内容は以下の通りです。
- 生活オリエンテーション:入国後の生活ルール、交通、医療機関などに関する情報提供。
- 住居確保の支援:賃貸物件の探し方、契約手続きのサポート。
- 日本語学習支援:日本語教室の紹介やオンライン学習ツールの提供。
- 相談・苦情対応:仕事や生活に関する相談に多言語で対応。
- 行政手続きの同行:役所での手続きのサポート
登録支援機関は、「
外国人材が日本で安心して働くための強力なサポーター」と言えるでしょう。
■信頼できる登録支援機関の選び方
登録支援機関を選ぶ際は、以下のポイントを重視しましょう。
- 実績と専門分野:特定技能制度における支援実績や、貴社の業種に対する専門知識があるか。特に介護分野など専門性が求められる場合、その分野での支援経験が豊富かを確認しましょう
。
- 費用体系:支援内容に見合った適正な費用設定か、不明瞭な費用がないか。
- 支援体制:多言語対応の可否、24時間対応など、外国人材のニーズに応えられる体制か。
- コンプライアンス意識:悪質なブローカーとの繋がりがないか、法令遵守を徹底しているか。
悪質なブローカーや詐欺を見分けるためには、実績や費用だけでなく、過去のトラブル事例や支援内容の透明性を確認することが重要です。
登録支援機関とは?人事担当者が失敗しない選び方と総額費用、新制度を徹底解説
採用後の定着支援とトラブル回避術

特定技能人材の採用は、入国がゴールではありません。日本での生活や仕事にスムーズに馴染み、長期的に定着してもらうための支援が非常に重要です。
「せっかく採用した人材に長く働いてもらいたい」「文化の違いによるトラブルを避けたい」と考える貴社にとって、定着支援は採用成功の要となります。
■日本での生活をサポートする義務とポイント
受入れ企業には、特定技能雇用契約に基づき、外国人材の日本での生活をサポートする義務があります。
- 住居の確保:安心して暮らせる住居の提供または支援。
- 銀行口座開設、携帯電話契約:生活に不可欠なインフラの利用をサポート。
- 役所手続き:住民登録や国民健康保険加入などの手続きに同行または情報提供。
- 生活オリエンテーション:日本のルールや習慣、災害時の対応などを説明。
これらの支援を丁寧に行うことが、外国人材の安心感に繋がり、定着率向上に直結します。
■日本語能力向上と文化理解促進の重要性
外国人材が日本で活躍するためには、日本語能力の向上と日本文化への理解が不可欠です。
- 日本語教育支援:地域の日本語教室の紹介、オンライン学習ツールの提供、社内での学習機会の創出などが有効です。特に介護分野では、利用者様との円滑なコミュニケーションがサービスの質を左右するため、積極的な日本語教育支援が求められます。
- 異文化理解促進:日本人従業員向けに異文化理解研修を実施したり、社内イベントを通じて交流の機会を設けたりすることで、相互理解を深めることができます。
【最新情報】MOC更新と今後の展望

特定技能制度は、社会情勢やニーズの変化に合わせて常に進化しています。最新情報を把握し、企業の採用戦略に活かすことが重要です。
■日本・インドネシア間の協力覚書(MOC)の最新動向
2024年6月25日、日本とインドネシアは特定技能に関する協力覚書(MOC)を更新しました。この更新は、両国間での特定技能人材の送り出し・受入れをさらに強化し、より円滑な制度運用を目指すものです。
MOCの更新により、人材の質保証や不正行為防止に向けた協力体制が強化されることが予測されます。これにより、受入れ企業はより安心してインドネシア人材を受け入れられるようになるでしょう。
日本国外務省およびインドネシア労働省の公式発表に基づき、STAYWORKERはMOCの最新情報を分析し、企業への影響を分かりやすく解説します。
■制度改正のポイントと企業への影響
特定技能制度全体でも、今後、さらなる見直しや分野拡大の議論が進められています。例えば、特定技能2号の対象分野拡大や、技能水準・日本語能力水準の変更などが検討される可能性があります。
企業としては、常に最新の制度改正動向をキャッチアップし、それに応じて採用計画や支援体制を柔軟に見直す必要があります。STAYWORKERは、公的機関が発信する最新情報をいち早く収集し、企業様に正確かつ分かりやすい形で提供することで、企業の採用活動をサポートいたします。
まとめ:インドネシア特定技能人材採用で貴社の人手不足を解消しませんか?

本記事では、インドネシア特定技能人材採用の「なぜ」から「どのように」まで、網羅的に解説しました。深刻な人手不足に直面する貴社にとって、インドネシア特定技能人材は、コストを抑えつつ、安定した労働力を確保し、事業を成長させるための強力な解決策となり得ます。
IPKOLやSISKOTKLNといったインドネシア政府公認システムへの対応、P3MIを介さない自社採用によるコスト削減、そして採用後のきめ細やかな定着支援まで、複雑な手続きや不安な点は多々あるかと存じます。
STAYWORKERは、最新の情報と豊富な実績に基づき、
厳選された人材の質、充実した支援体制、高いマッチング精度を強みとして、企業のインドネシア特定技能人材採用を成功へと導くための最適なパートナーです。
執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平
監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志
株式会社USEN WORKINGの外国人採用コンサルタント。人材紹介・派遣の法人営業として多くの企業の採用課題に、そして飲食店経営者として現場のリアルに、長年向き合ってきた経験を持つ。採用のプロと経営者、双方の視点から生まれる具体的かつ実践的な提案を信条とし、2022年の入社以来、介護・外食分野を中心に数多くの企業の外国人採用を成功に導く。